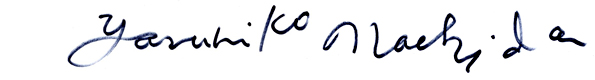Perfect Days
月曜日, 5 2月 2024

“The House of the Rising Sun” Alan Price
“Pale Bluer Eyes” The Velvet Underground
“The Dock of the Bay” Steve Cropper
“Redondo Beach” Patti Smith
“Sleepy City” The Rolling Stones
“青い魚” 金延幸子
“Perfect Day” Lou Reed
“Sunny Afternoon” Ray Davies
“Brown Eyed Girl” Van Morrison
“Feeling Good” Nina Simone
これはヴェンダースの最新作「perfect days」に使われている音楽リストだ。僕は、小学生の高学年から洋楽を聴くようになったから、60年代や70年代のこれらの音楽をリアルタイムではないにせよよく聴いてきた。僕に限らず日本で洋楽を聴いていた人たちは(好きか嫌いかは別にして)おそらく100%に近い確率でこれらの音楽を通過してきたはずだ。当時はグローバルミュージックとこれらの音楽のことを言わなかったと思うけれど、昨今そう呼ばれている音楽などよりもよほど「われわれ」にとって「コモン」なものだった。何せ情報も偏っていたし、ミュージックシーンの多様化も今ほどではなく選択肢は限られていたからだ
良いか悪いかの話ではなく、70歳手前のヴェンダースさんや役所広司さんが60〜70年代を懐かしむように、今の若者が70歳になって振り返り懐かしむような「共通世界」などおそらく存在しない。今、時代は相対化、多様化していて「われわれはあの音楽群を聴いて育った」とか「われわれはあの映画群を観て育った」とかって彼らが語ることはないはずだ
そんな「それぞれ」の時代にあって、かつて西欧近代が理想として掲げた「われわれにとっての共通世界」を実現しようとするような気力を引退間近の人間に求めるのは酷なのかもしれないと思う。むしろ、そんな馬鹿げた理想から「サレンダー」したヴェンダースに拍手を送りたい気持ちもある。僕だって、全体性に包まれるような世界がわれわれの前に現れるその瞬間を手繰り寄せる努力を、半分は諦め、やめているから。でも、諦め切れないでいるもう半分の自分がこの映画を見て「ふざけんじゃない」と憤っている。世界の和平を実現するという口実で、さんざん世界の構造をいじりまくって近代を押し付けてきた西欧の側が、最後の最後に衰えて「和平はそれぞれの心の中にある」みたいなことを言うんじゃない、と。そんなことは茶の間でティーでも飲みながら自分のパートナー相手に語っておけ、と
だから、僕にとってこの映画は衰えた近代からの「手打ち」の映画に映る。しかし、その手打ちの言葉を発したヴェンダースは数々の映画を撮ってきた優れた作家。僕は、やっぱり彼のような世代が作った映画を20〜30代に浴びるように観て育ってきたと思っている。彼の言葉はゆるゆると、かつて聴き込んだ音の調べと一緒くたになって僕の内部にこんな風に染み込んでくる。「ああ、僕もあなたも共に失敗したね」「失敗した、ということであなたと私は共にある」。まるで茶の間に呼ばれてティーを差し出されているかのような気持ちになる
ああ、そうだ、僕も失敗し続けているよ
きっと明日も失敗するだろう
「でも、でも」とわけもわからず涙目になる。映画の中で役所広司が浮かべる涙と、僕が今、浮かべている涙とにどれくらいの差異があるのかそんなことはわからない。わからないけれども、ただ悲しいから泣く、とか、嬉しいから泣く、とかってことではなくわからないまま涙が出るということがわれわれ人間には起こる。複雑さを生きる、生き続ける、生き続けたからって答えなどきっと現れてこないけれど、死をかたわらに置きながら生き続けてみたい、と、そう思っている。もしかしたらヴェンダースも、この映画を撮り終えてそんな気分なのかもしれない、と思う
なんだかんだ21世紀ももうすぐ1/4が過ぎてしまう。この先を、われわれはどのように生きていくのだろうか