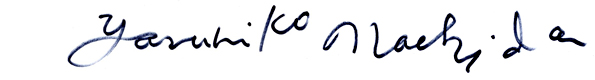方丈記私記[平成]
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.023(完結)
「コロナの感染者数」を数えるのに忙しくしている間にも、人は違う感性で東日本大震災から10という年月を数えていた。その10という数字をどのように捉えるのかは人ぞれぞれだけれど、私自身はがらがむしゃらに生きてきてちょっと感慨深くいて、令和3年の3月11日は特別な過ごし方をしたいような気がしたのだった
阪神淡路大震災の時は祖母が神戸で被災して「大変だ、大変だ」と私も現場に駆けつけカラ騒ぎしたけれど、あの日から積み上がっている年数は私の中ですでに白濁として定かではない(平成7年1月17日から冷静に数えれば26年が過ぎていると振り返ることはできる)。西ノ宮で生き埋めになった祖母が昨年100歳に達したことを(コロナ禍なのでオンラインで)親戚一同で祝ったけれど、もはや阪神淡路大震災は祖母の人生の中で数ある出来事のひとつとして処理され色褪せてしまっているのかもしれない。私も東日本大震災が起きてから数字を足していき、同じようにいずれはそれが記憶の中で薄くなっていくことは目に見えていて、でもそうなった時、私はどこでどんな生活を送っているのかと彼女の顔を見て不思議な気持ちになった。100歳とは言わないまでも60歳くらいになっていて、孫に還暦のお祝いをしてもらったりしていることもあるのだろうか。なんとなく、60歳まで生きることを前提にしてものを語ることの難しさを、今、感じている。どちらにしても「あれから何年」と311から数字を勘定しているのはジジツとして、正直なところ、度重なる災害や人災が降りかかるその都度それぞれを必死になって切り抜けるしか道はなく、まぎれて大震災の記憶は薄まりつつある。つまり、おそらくそれをジッカンしているからこそ、10という数字の節目においてどこでどう過ごそうかと改めて考えようとしたわけなのだ
そして、個人的な(内面の)揺れが他人の揺れに同調してしまう時間をあえて過ごすより、個人的な揺れは個人的な揺れとしてしっかりと感じていたいと思ったから、色々と考えて、震災直後に訪れた南相馬の喫茶ウェリントンでコーヒーでも飲みながらひとり過ごすこととした
「喫茶ウェリントン」ここにそう書くだけで感慨深いものが湧いてくる
映画を撮るための視察を兼ねて津波が襲った地域を車であちこち走破したのが2011年の春だった。相馬は、漏れ出る放射能による影響で立入禁止区域が網の目状に伸びていたためアクセスが難しかった。宮城県の方へとぐるっと迂回しつつ北から降りるようにしてどうにか立ち寄ることができたのだけれど、ちょうどお昼時なのに空いている飲食店はほとんどなくて(もちろんそうだろう、多くの住民が避難したわけだし観光客などいるわけはない)、それでもどうにか営業していた店が喫茶ウェリントンだった
一種独特な空気が充満していた当時の福島にあって、生活の匂いがするその喫茶店を見つけ吸い寄せられるように中に入って、私は、救われる思いがしたのだった(※1)
それから、私は喫茶ウェリントンを再訪できずにいたからほぼ10年ぶりにお父さんが入れてくれるコーヒーを飲むことになるはずだった。だった、と書くにはもちろん理由があって、結論から言うと店はもうなくなっていた。同じ場所には、真新しい南相馬市民文化会館が建っていた。現地でネットを使って調べると、立退があった後も喫茶店は一度位置を変えて営業を続けたようだけれど、2年前にその店も(別の人が経営する)カレー屋に取って代わられた。私はもっと早くに再訪できなかったことを小さく悔いたけれど、なくなってみて、10年という年月の長さを改めて思い知った。あの時は喫茶ウェリントンだけが店を開けていて、今は、あらゆる店が営業しているというのにウェリントンだけが姿を消してなくなっている。10年前、私が「ウェリントン(※2)には行ったことがあるんですか?」と女将さんに問うと、顔を赤らめながら「行ったことがないんです。でもいつかは行ってみたいと思っているの」と返事をしてくれた。今、喫茶店をやっていた夫婦がどうしているのかはわかりようがないけれど、喫茶店をやめていの一番でウェリントンへと旅したことを他人事ながら期待する。そして、許されのであればいつか彼女たちの旅の話を聞いてみたいと願う。今、コロナ禍で、海外へと行くことのハードルは随分と上がったように感じるからなおさらだ
それはそれとして、「2時46分」を時計の針が通過するその瞬間を過ごすべく場所の当てがなくなって、私は、途方に暮れた。海でも見ながら、とも思ったけれどそれはそれで私の揺れとは違う「波」に同調することになるかもしれず、どうしようか、と考えあぐねながらとにかく海の方向へと車を走らせていると、桜井古墳群なる遺跡に出くわしたのだった。時刻も迫っていたから「せっかくの出会いなので」と、迷わず私は前方後方墳の上に立った
長さが75メートルある東北最大級の墓の上に立つと、四方がしっかりと見渡せて「ここでよかった」と胸を撫で下ろした。西には喫茶ウェリントンがかつてあった町の賑わいが感じられ、その先に阿武隈山地が臨めた。南には別の町の賑わいがあり、北には新田川とそれを利用した水田が広がっているのが見えた。そして東には川が流れ着く先の太平洋がかすかに見えた。いや、つまり、人の営みに関わる全てのものがここから見渡せたのだった。私は、新田川の流れを見ながら茫々とした意識で、土地に、ほんのひとときに現れるひとつの生活の儚さ、みたいなことを感じていた。喫茶ウェリントンは私の世界に現れて、そして幻だったかのように綺麗さっぱりと世界からなくなった。きっとどの時代のどんなものも、誰かが軽く瞬きをするような感じで、あることとなり、そしてなくなる
しかしそう感じる私は4世紀に建てられた墓の上に立って、古代の人も見ていた新田川を現代に見ている。それは紛れもなく同じ川で、その流れは絶えずあったはずだ。しかし、くどいようだけれども、そう、そこを流れる水はしかしもとの水ではない
「ウーン」と方々から一斉に汽笛のようなサイレンの音がこだまして、私は、きっかり令和3年3月11日2時46分に、我に返った。「我」に返った私はその時、でも、誰の目でもいいような目を瞑り黙祷を捧げ、誰の耳でもいいような耳で風や鳥のさえずる音に混ざるサイレンを聴いたのだった
・・・・・・・・・・
今まで平成に起きた災害や人災による死亡者数や被害の数を記してきた『方丈記私記[平成]』だったわけだけれど、最後を締め括るのにそれらとは違う「何か」を数えたくなっていた私は、「喫茶ウェリント」までの道程で渡った川の数を数えることとしたのだった。そのいたく個人的な記録を残し『私記』を終わりにしようと思う。相馬に向けて益子町を出発した私が渡った最初の川は隣町を流れる逆川で、そこから数えて84の川を渡り南相馬に辿り着いた。ひとまずどんな太さの川も「ひとつ」と数えたけれど、見落としたものもひとつやふたつあるかもしれない。世の中に名前のつかない川があるのか知りもしないけれど、渡った川で名前を知ることができたものをここに書いておく(本流、支流を含めて複数回渡った川の記載は1度とする)
逆川、那珂川、大沢川、緒川、玉川、久慈川、浅川、山田川、里川、入四間川、十王川、小石川、花貫川、多々良場川、関根川、塩田川、大北川、江戸上川、里根川、蛭田川、豊川、鮫川、渋川、藤原川、釜戸川、藤原川、矢田川、滑津川、夏井川、横川、小久川、大久川、折木川、浅見川、木戸川、井出川、富岡川、熊川、高瀬川、請戸川、宮田川、小高川、前川、太田川
川の数を数えることなどにもちろん意味はない。意味などないけれど、その意味のなさに安堵している私が確かにここにいる。あらゆるものに意味がないことを受け入れつつ生を開いていくのか、それとも何かしらの意味が得られることを信じてゼロから数字をひとつひとつ積み上げていくのか、そのふたつの道はそれほどまでにも違ものなのか。そもそも、数字を積み上げることを受け入れるそのことこそが生活ということなのかもしれないとさえ思えば、私は、この世に生を受けていったい何をしているのだろう、自分のことだけれど、まったくわからない。わからないからひとまず数字を数え上げるけれど、やっぱり何度も挫折して「無理だ」と私はゼロへと落ちていく。ゼロへと落ちていく時、私は、、、
その時、心はさらには答えなかった。そうであるならば、、、
今はただ、答えない心のかたわらに、つかの間の舌のちからを借りて、心のあずかり知らない南無阿弥陀仏を、三べんほど唱えて、この暁(あかつき)の随筆を、静かに終わりにしようか。
これは、鴨長明が『方丈記』を締めくくる時に書いたことである
そして『方丈記私記[平成]』に、私が最後に書いていることである
(※1)その時のことを『喫茶ウェリントン』という文章で「ミチカケ」にて発表しました。noteにもアップしているのでもしよかったら読んでみてください
(※2)ウェリントンはニュージーランドの首都
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]番外編
NO.022の<前半>を書いてからコロナ(の流行)があって、時間ができたから<後半>を書こうと何度か試みたけれどどうしても書けなかった。そのうち、書くモチベーションも失せてしまって気がついたらもう夏が終わっていた。それでも、書けるような気がすればその都度に筆を持ってやってみたのだったけれど、やっぱり書けなかったし、今もって書けないでいる
2020年のオリンピックまでの3年間は書き続けると2017年から初めた『方丈記私記』だからそのオリンピックが中止となって書くあてがなくなった、ということでは決してない。この(原発事故の後処理も終わらない)日本で「オリンピックを開催する」という戯言が文字通り戯言であったということがはっきりとしただけなのだ、改めて驚くほどのことではない。ただ、同じように「目に見えない」放射能という洗礼を世界よりも一足先に浴びていたわれわれの社会の秩序が、コロナの(もしくはコロナの存在するこの世界の)なにを言い当てているわけでもない感染者数という「数字」によってその根底から揺るがされている、ということにはそれなりに驚いた。しかし、(ここまでの状況にならないと変化が起きないのかという落胆はあるにしても)コロナをきっかけとして(原発事故をきっかけとして果たされると思った)変化が確かにわれわれの社会にやって来たことは、素直に嬉しい
現実を生きるのは、もちろんこの私である
同じように、夢を見るのも、この私である
夢で、現実の世界で生きるように生きるのは、私である
現実で、夢の世界で生きるように生きるのは、私である
私が見た夢を外から覗き込んでそこから[私の無意識]をピンセットでもってぴょんとつまみ上げるのは、現実の世界のあなた(精神科医)の仕事であるのかもしれない。しかし、私は、私の内側から夢を見ているのであって、私の外から夢を見ているのではない。だから夢に立ち現れる私の無意識は、外の世界であなたによってぴょんとつまみ上げられる[私の無意識]とはちょっと違う。外の世界から「これはあーだ」と指摘される[私の無意識]は、[私]に囲われ縛られて、その[私]からとっても不自由だ。けれども当の私の無意識はというと、[私]なんかと呼ばれるモノからも自由なはずである。そして私から自由な私の無意識は、つまりのところただの自然なのである。しかしいい置くまでもないけれど、この自然は、その一部が人類としての[私]であることを拒んだりなんかしない、つまりそういう種類の自然である。外からぴょんとつまみ上げられて顕微鏡なんかで観察される、あのぴたりと止まった[自然]なんかではなないのである
隠れていた自然が、「ん?」という顔をしてこっちを見ている。そしてちらりと覗き見るその顔は、[自然]と名づけられる前の自然の顔なのだ。私は今の世界に顕然する変化をそんな風に感じている
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]番外編
コロナは人の意識である、と書くと「いや、コロナはウィルスだ」と反論されてしまうかもしれない。しかし、コロナがウィルスであるのは、その対象を科学的、もしくは生物学的(ウィルスが生物かどうかということには決着がついていないのかな?)に見る時に限ってである。日頃の生活において、コロナは我々の目には見えない。その見えないコロナについて、日々、隣の人と語り合うのは、もしくは電車の中で握った吊革がいつもよりも不潔に思えるのは、人の意識がコロナと同調しているからである
今、自分の目の前に見えるのは、育ち過ぎた白菜が黄色い花を咲かせているところである。そこに、近所の養蜂家の巣箱からやってきた蜜蜂がその蜜を吸いに来ているのが見える。ウグイスが、とても上手にホーホケキョと鳴いているのが聴こえる。中国から渡ってきたガビチョウがギーギーうるさい。遠くで、チェンソーの音がする。それは、近所の陶芸家が腐ったウッドデッキを直している作業音である(先日、犬の散歩の時に声をかけたので知っている)。空を自由に飛ぶ鳥や蜜蜂に、そして聴こえるさまざまな音に意識をはわせると、私の世界はぐっと広がる。目に見える世界、普段自分が世界だと思っている世界の広さよりも、意識の世界はシームレスで、もっともっと広い。目に見える世界、耳に聴こえる世界だって「わたし」の世界を広くしてくれるのだから、目に見えないコロナに寄り添うと、「わたし」はミクロマクロ両方の全世界に浸透可能となる。ニューヨークで、スイスで、ドイツでそれぞれの部屋に篭っている友人がいるから、「わたし」の意識はそこにまでやすやすと到達するし、日頃手を洗わない僕が手を洗うようになり、免疫について考えるようになった。コロナが「わたし」にしてくれた素敵なことの一つである
コロナは意識で、しかも世界が広いから、同調しすぎてしまうとなかなか「ここ」に戻ってこられないという弊害が起きる。意識は意識であるのだから、意識は(本来的には)意識的にコントロールできるものである。ウィルスとしてのコロナとは違って、意識としてのコロナは「エブリシング・イズ・アンダーコントロール」なのである
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.022(前半)
幼少期から青年期に渡って、私は、真言宗系の新興宗教に入信していた。自分の意志で入信していたというよりも、信者だった親に連れられ時たま道場へ行くくらいの中途半端なものだった。それでも、家で読経をする事もなくはなかった。宗教団体の道場の雰囲気は独特で、なにか「特別」な感じを体験させられた。「ここ」に含まれていれば「安全」なのかもしれない、子供ながらそんな風に思ったことを覚えている。幼少期の頃はおそらくは他人より自然との親和性を深く感じていた不思議ちゃんでもあったから、対話の相手を「シゼン」から「ホトケサマ」へと変えることに、あまり違和感を感じなかった。死んだ鳥を拾ったら埋めてやり、そして念仏を唱えて空にかかる虹を愛でる、そんな具合に、私にとっては自然も、宗教も、大差ないものだった
そんな「私」の世界に大きな変化が訪れたのは小学校3年生の頃だった。親の都合でニュージーランドへと引っ越したのだ。当時のニュージーランドは、イギリスからの移民が大半を占めていて、そこに原住民であるマオリ族が一割り程度混ざり込んでいた。「ここ」に含まれていれば安全だと思っていた「私」の世界に、「神様」と「西欧人(アングロサクソン)」、さらには「アニミズム」と「マオリ」が入り込んで来たのだから、内面は、まさにカオスだった。今、振り返ってもこのパラダイムシフトは劇的で、その環境がそもそも不思議なのだから、と私自身が(自作自演的な)不思議さに生きる事を自分に許す結果となった。日本語の通じない(私の側からしてみたら)外人から身を守り、価値観の違う社会の外圧から避難するその先は、文字通りに「夢の中」だった
私は、この頃(不思議ちゃん度合いを深化させ)夢の中に生きることを覚えた。9歳から11歳くらいにかけての事だろうか。夜、布団に入って目をつむり幾らの時間もかけずに私は夢の中に音もなく入っていけた。夢の世界に入ると日本人の友達を誘い、一緒にその日の遊びの続きをした。飛ぶこともできたから、違う友達の家までは空の上。遊びの最中、不測に危険なことが起きたとしたらちょこんと足のつま先を揺すって目覚めることも自分の意志のままだった。魂との出会いとしてのエロスもまた、夢の中にあった。そう、全ての事が過不足なく夢の中にはあった
ただしばらくして、現実というものが夢の世界の隅々にまで浸透してしまっていることと同じように夢というものが現実の世界の隅々にも浸透している、という当たり前の事に私はとつと気がついた。だから、「怖い怖い」と思っていた現実をも白昼夢に生きるような感覚で過ごすことができるように徐々になり、夢に避難し遊んでいた私は、次第、現実の世界に、己の足で、己の意志でもって出て行って、楽しく遊べるようになっていった。夢と現実との境は、とても薄い幕ひとつで仕切られていた
13歳となって、親の仕事の都合で家族は日本へと帰国することになったけれど、私は、家族と別れてニュージーランドに残ることを、自己決定した。しかも、かつて家族が住んだ首都ウェリントンからバスで数時間のところにあるウッドベリーファームと名づけられた牧場で仕事をしながら遊んで過ごすことを選択した。そこでの数ヶ月は私の記憶の中で「特別」な位置を占めていて、未だに目映いばかりに光り輝いている。そしてそれは今も「そこ」にあり、そしていつだって「ここ」に蘇ってくる
与えられたダットサンのトラックを不慣れながらも運転し、何十ヘクタールとある農地を疾走した。勢い余って土手に突っ込み横転しそうになって車が片輪走行するその時の危ういバランスが、まだ、私の身体に残っている。羊や牛と戯れつつ、一緒に働いていた栗色をしたくせ毛の女の子に仕事を教えてもらいながら、仕事仲間といろいろな話をした。今振り返ってみても、どうして私がその牧場で(仕事を手伝っていたにしても)あそこまで勝手気侭に振る舞うことができたのか、とても不思議なことだと改めて思う。試作されていた日本の梨を美味しくって懐かしくって木まるごと全部食べ尽くしてしまっても叱られることはなかった。柵を閉め忘れて囲っていた百の羊を逃がしてしまっても、本物のM16でスイカを撃ちまくるような悪戯をしても、トラクターをぶつけて建物と機械の両方を壊してしまっても、牧場主は、私を一度も叱らなかった
わんわんわん、と私が逃がした羊を囲いの中に追い込む牧羊犬はかっこよく、そしてとても美しかった。その犬を口笛で上手に操る牧場主もまた、とてもかっこよかった。ウッドベリーファームは、まさに、隅々にまで夢が浸透した世界そのものだった。そんなことをジッカンさせてくれる、私にとってはかけがえのない特別な場所だった
そして、ここでの経験によって、宗教団体の道場で感じた「安全」な「感じ」は、現実の世界でも「自己」決定的に選択できるということを、私は知った
ただ、そんな黄金期にあった私も、社会的にはまだ義務教育期間中の中学生だった。親元を離れて遊んでいるにも制度的な限度があったのだろう、私は、日本に帰国して公立の中学校に転入する必要があった。そして、夢の続きを見ていたような心地にあった私が、日本の中学校の最初の体育の授業で整列をさせられ「マエナラエ、ミギムケミギ」と号令によってまるで羊のように「動かされた」時の私の受けた衝撃といったら筆舌に尽くし難い。「ミギムケミギ」に戸惑う私はいじめっ子に「ちゃんとやれよ」といじめられ、中学3年生の半年間は、「これがただの悪夢であってくれたなら」と毎朝心の底から願う中で起床した。「安全」な「感じ」からほど遠かったあの時の毎朝は、やっぱり私の記憶の中で「特別」な位置を占めている
私は、その頃、もう夢の中へと逃げ込む技術を失っていた。だから中学3年生の私の目の前にあったのはただのつまらない現実だけだった。それでもその現実を白昼夢を見るようにしてやり過ごす技術は手放していなかったから、私は、半ば、自然科学者のような態度でつまらぬ現実を自分のことからばっさりと切り離し、日々を、観察するように過ごした。靴下にワンポイントの柄が入っていて、ヤンキーに叱られた。制服の袖をまくっては、それは不良の特権だ、とたしなめられた。ぼうぼうとした意識でたんたんと観察をすればそれら全ては、喜劇の世界だった。だから私は求められる通り、喜劇の中で道化師を演じた。今の私にある道化の性質は、転校を重ねて身に付けた自己保身によって染み付いた癖なのだ
1989年、東京の中目黒にある中学校に在学していた最中、当時の小渕官房長官が「平成」という新しい年号を発表した。私にとっての黄金期であった昭和は14年間(1975年〜)で終わり、そして、笑えない喜劇のような平成がこの時に始まった
ニュージーランドには私が所属していた宗教団体の道場がなかったけれど、帰国してその道場があったから、私は、失った「安全」を求めて改めてそこに通うようになった。そして、多分この頃から強迫観念にかられたように、私は、家でも(こっそりと)「読経」をするようになった。不思議ちゃんとして、社会との折り合いがつかない事がジッカンされればされるほど、社会の中での「罪と罰」を意識した上で「許されたい」と思う欲望が強くなっていった。「今、これだけ不安を抱えているのは、自分に至らないところがあるからだし、受けるべき罰が存在するから」そんなことばかりを考えて過ごした。それと、物心ついた頃から「なぜ何もないのではなく、何かがあるのか?(Why is there something rather than nothing?)」という疑問も付き纏っていたものだから、宗教は、その答えを得るための道筋を示してくれるはずだ、ともずっと思っていた
後に知った事だけれど、紀元前500年に生きたパルメニデスの発したこの言葉と同じような疑問を呟く者に対し、神学者のアウグスティヌスはこう断罪したと言う「そんな質問をする者のために、神は地獄を創ったのだ ※1」と。これもまた、笑えない喜劇のような話しのひとつである
宗教をやっていた頃は、常に「善悪」が私の行動原理にあった。だから、生きていていつだってとても窮屈な感じがしていた。何が善で何が悪か、その色分けをする能力を有する人になりたいと思っていた。まさかそれら両者が分かち難く矛盾しながらも同一に存在している事など、その頃は、考えもしなかった。お経を何度読だところで、子供の頃に夢の中で感じた「安全」はやってこなかったし、おまじないとしての効果も感じられなかった。ウッドベリーファームでジッカンした全体性も、その後は一度も私を包むことはなかった。私が頭の中でこしらえたホトケサマは、ウッドベリーファームの牧場主のようには、私をなかなか許してはくれなかった。子供から青年になって、眠れぬ夜、私は、ウッドベリーファームで逃がしてしまった羊を、いち、に、さん、とその数を数えながら探すことがあった。私の現実には牧羊犬がいないから、逃げた羊はなかなか囲いの中に集まってくれなかった
今思えば、その頃の夢と現実の境界は、かつてないほどに強固だった。「夢と現実をちゃんと区別しなさい」そう諭すような大人など私のまわりにはひとりも居なかったというのに、私は、勝手にその境界を強固に(自己決定)したのだった
※1実際には、アウグスティヌスはこのようなことを言ってはいない。むしろ「何か」について知ったような事を言う聖職者に対し、アウグスティヌスはこのように諭した。「わたしは神秘を究明したものを嘲笑し、虚偽を答えたものを称賛するような答を与えるよりは、むしろ知らないことは知らないと答えよう」そんな誠実な人だったようだ(岩波文庫『告白』を参照)このように、笑えない喜劇はいつだって悪気のない純粋な人によって語らるのだ
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.021
2017年(平成29年)の自分の誕生日(3月5日)に、この方丈記私記[平成]を書き始めた
当初、オリンピックが行われる2020年までの3年間、とにかく書き続けることを自分に課したのだったけれど、気がつけばもうその3年が経とうとしている。あっという間と言っても嘘にはならないけれど、しかし振り返って、あっという間と言うには、やはり、様々な災害があったし、そして、うんざりするくらいのシステムエラーやヒューマンエラーを目の当たりにもした
いや、それら人為的なエラー、劣化した感情の発露にはもううんざりすることにも飽きているのだけれど、それでも隠せないほどの衝撃を受けた(受けている)のは、平成最後の夏、合計13名の死刑囚の刑の執行がほぼ同時期に二回に分けて執り行われたジジツであった(ある)。いい置く必要もないと思うけれど、その13名とは、オウム真理教という呼称で当時存在していた宗教団体の信者もしくは構成員で、その組織が起こした複数の殺人事件(および殺人未遂事件)などにより死刑判決を言い渡されていた(麻原彰晃こと松本智津夫を含む)その人たちのことである
方丈記私記を書き始めたその最初から、阪神淡路大震災と地下鉄サリン事件のあった1995年(平成7年)について書くことになるだろうことは、もちろん分かり切っていたことだったけれど、まさかそのことを書く前に(平成が終わる前に)臭いモノに蓋を閉めるかの如く、そして平成の事件は平成のうちにカタチだけでもカタを付けたいとばかりに、まるで戦後直後の東京裁判よろしく矢継ぎ早に刑が執行されるなどとは(個人的には)微塵も思っていなかった。微塵も思っていなかったことの根拠をいくつか上げるとすれば、彼ら13名中10名が再審を請求している途中だったから、ということもあったし、ましてや13名の中には殺人を犯していない人も含まれていたからだ。さらに、彼らよりも先に死刑が確定していた(オーム事件とは関係ない)囚人がかなりの数いて、順番的!にまだまだだ、ということも認識していた、つまり一言で言うと、政治パフォーマンスのために死刑制度がここまでおおっぴらに利用されるようなことがまかり通るとは、思えなかったのだ
死刑を執行したその判断の中に「法に基づいて成されているから客観的に正しい」などと思える要素はほとんど見当たらず、(そもそも法を根拠に自分が客観的だという人を僕はその時点で信頼しない)これは、端的に言って組織を狙い撃ちにした魔女刈り的な要素が強い
それで、それこそ私自身もノルマとしている3年間のうちに平成7年のことを書きたいと思うけれど、オウム真理教が起こした事件について書くことの「荷」は、死刑が執行されたことで何倍にも重くなってしまった。その上、この(自称)連載には、(当たり前だけれど)編集者や内容を照査してくれるパートナーが関与しているわけでもないから「至らない」のがとても怖くって、筆が鈍る。トウゼン、書かないという選択肢もあり得るのだけれど、死刑制度の存在を結果的に許してしまっている私はつまり、首が吊るされる際に死刑囚を台から落とす(そう、ここまで科学が発展しているというのに日本の死刑は未だに絞首刑なのだ)操作ボタンを、半分は自分で押しているようなものだと思っているし(実際にそのボタンを押している人がいて、その負担を軽視しているわけではないけれど、でも、やっぱり思いが及んでいない書き方であると思う)、ましてやオーム真理教が起こした一連の事件に関しても(私は信者でも構成員でもなかったけれど)、実行していたのが自分であってもおかしくないような要素が沢山あり(時代を共有していたという意味で)、この事件を知らずに成人する人が増えていく世の中にあって「方丈記私記」を書く者として(ずいぶん勝手な物言いだけれど)やはり他人事では済まされないと思っている
と、ここまえ書いてみて、やっぱり一連のことをどう書き始めていいのか、わからないでいる
もちろん、坂本弁護士一家殺害事件や松本サリン事件、地下鉄サリン事件の詳細からつらつらと書き始めてもいいのだけれど、その先に起こった「死刑」にいたる経緯にわからないことが多すぎて、書き始めたその始めから迷子になること必至である。どうして、刑が執行されてしまったのか、刑を執行してもよかったと思えたその発想の発端がどこにあったのか、まったくわからない。そもそもどうして日本から死刑制度がなくならないのかが、まったく、わからない。刑の執行を許可した(書類に印を押した)川上陽子法務大臣が、刑が執行される前日に料亭で気持ちよく楽しく忙しくお酒が飲めた理由がわからない。さらには、一連の死刑が、二回に分けて施行された理由がわからない。1回目と2回目の間に空いた3週間、刑が執行されるのを待っていた囚人は、(1回目の執行がされたことを知りつつ)どんなことを考えて過ごせばよかったのか、その「模範例」のひとつも思い浮かばない。映画が描くように「死ぬまでにしたい10のこと」のたったひとつでもやれることが適わない世界で、彼らは、なにを思いながら「次」が来るのを待てばよかったのだろう。世の中は芸能人の「不倫」のことで賑わっているようだけれど、川上陽子のしでかした「(倫理から大きく外れた)不倫」が芸能人の「(ちょっと道徳から外れている)不倫」よりも騒がれないで済まされてしまっている理由が、どうしても、わからない(そもそもだれそれの不倫について語れるほど、われわれは「正しさ」についてのあれこれを、ちゃんと考え、議論したことがあるのだろうか)
なんもかんも、わからない
書き始めて3年が経とうとしていて終わりが近づいたのかと言うと、もう、始まりにも到達していない気持ちでいる。私が、東日本大震災の直後、5年に渡ってハトの撮影を続けたのは、集団化していく真理やその過程をどうにか目に見えるカタチで(批判的にではなく)提示することの可能性を直感的に感じたからだったけれど、ハトの集団意識など、人間のと較べたらとてもかわいく慎ましいものであった。しかし、もしわれわれが「われわれは、ハトなどとは違う」と言うことができるとしたら、それは自分が集団意識とやらに絡めとられているということに、自立した個人として「気がつくこと」であるのだろう。言ってしまえば、たったそれだけのことなのだ
地方を旅すると、よく、鬼の伝説が残る場所にでくわす。今の時代に「鬼」は、フィクションとして処理されるけれど、しかし、ここまで広範囲にしかも多発的に鬼の伝説が残されていることを考えると、むしろ、当時は確かに鬼がいたのだ、と言うことのほうが遥かに説得力があるように思う。しからばその「鬼」とはなんだったのか、それは集団意識が見た「雨を降らし雷を鳴らす何か」だったのかもしれないし、はたまた馴染みのない宗教を携えてやってきた、ちょっとだけ赤い肌をした移民だったのかもしれない
しからば、われわれの時代が見ている「鬼」は、なんなのか
それはやっぱり100年たった後にしかわからないものなのか、いや、私は、断固としてそうは思わない。なぜなら、今いる「鬼」を見ているのは、今に生きる「わたし」に違いないのだから
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.020
私が学生だった頃(平成元年から10年間)の交通事故死者数はほぼほぼ毎年10,000を超えていた。それに対して令和元年(平成30年)の交通事故による死者数は、ぐっと減って3215人だったそうだ(警察庁の統計による)。交通事故死者数の減少は、モノとしての車の性能が向上したのに加えて、シートベルトの着用が義務づけられたこと、また飲酒運転の厳罰化などによる法規的な効果(システムの向上)が原因だ、と誰かがそう述べれば、うん、そうだろうね、と納得するひとが多いに違いない。私自身が日々車を運転している生活においてジッカンされることと照らし合わせても、確かにそれらの因果は認められるような気がする
同じように私が学生だった頃の自殺による死者数は毎年30,000人近くまでのぼった。団塊の世代、そして団塊ジュニアの世代の自殺率は共に高かく、私自身も昭和50年の早生まれで団塊ジュニアの世代に含まれるため、それこそ生活ジッカンとしてその数が「多くある」ということは、強く感じている。例に漏れず、私の同級生も7人ほど自殺で死んでいるし、父の同級生にも何人かいたことを本人から聞いている
その自殺者の数が東日本大震災があった平成23年を境に、統計上は減少している。震災から8年ほどが経過して令和元年(平成30年)に、その数は、2万人ほどまでに減ったのだという(警察庁および厚生労働省の統計による)。減少の原因は、もしかしたら(自殺を選択していた)団塊のひとたちが高齢化して自殺をするまでもなくなった(つまり私の父がそうであったように病死するようになった)から、安倍政権が主張するよう(非正規ながらも)雇用が改善した上に自殺対策が行き届いてきたから、とさまざまなそれらしい原因を挙げることができるかもしれないけれど、うん、そうだよね、と素直に思えないのは、とどのつまり過去と比べて現在がより生きやすい社会になった、という生活におけるジッカンが持てないからだろう
人によっては、「変死体」の数が増え続けている(警視庁の「死体取扱数等の推移」によると平成15年からの10年間で9,000体ほど増えている)ジジツを持ち出して自殺者の数が減っていないことを主張することもありえるだろう。国際的には、変死体の一部を自殺者としてカウントして然るべきようだけれど、日本ではそれをしないため、現実的には統計が示す数よりも自殺者の数が多いことは間違いないようだ(遺書のない自殺は変死体と数えられる)
どちらにしても、自殺者の数が50,000人なのかはたまた20,000人なのか、実際の数に近い数を知るのはそれを数えている者だけだ、ともなかなか言えそうにないのは、それを数える者だって、システムに応じて自殺か他殺か事故死か変死かを全くもってジュンスイな気持ちで、いち、に、さんと機械的にやっているだけのはずだからだ
いち、に、さん、し、ご、、、
そうやって数えられた数は、数が数え始められたその最初から、1なら1という意味を、2なら2という意味を(たぶんきっと)変えたことがない。いち、に、さんと数を数え始めてからその「数」を手放すことがなかったということは、いち、に、さんと数を数えることを、または「数」そのものに価値を見いだしたからである(そして、私はその価値を半ば呪っている)。つまり、1そのものの価値は動かずあり続けた。しかし、1の「社会的」な価値はずんずんと下がりつづけているのが現状なのだろう。自殺者の数が50,000と言われようが20,000と言われようが(社会的な思惑が背景に透けて見えるから)そういった数を見聞きしたとしても双方それぞれの意見ががちゃがちゃといつまでたってもあるだけで、結局最後は「数なんてしょせん数に過ぎない」と互いがココロのなかで思ったりしているのだろうから。ただ、繰り返すけれど、数そのものの価値が減ったわけではない。東日本大震災で亡くなった人の数は、震災に関連する自殺者を含めて15,898人(平成30年9月10日時点)に達し、「ああ、そんなにも尊い命が失われたのか」と、われわれは(特に東日本の人間は)、ぴったり正確に毎年3月11日の午後2時46分に、いっせーのせっと意識を合わせ黙祷を捧げたりするのである
鴨長明は、養和元年に起きた大飢饉について『方丈記』に以下のように書いている
仁和寺に隆暁法院(りうげうほふいん)といふ人、かくしつつ数も知らず死ぬる事を悲しみて、その首の見ゆるごとに、額に阿字を書きて、縁を結ばしむるわざをなんせられける。人数を知らむとて、四・五両月を数へたりければ、京のうち、一条よりは南、九条より北、京極よりは西、朱雀よりは東の、路のほとりなる頭、すべて四万二千三百余りなんありける。いはむや、その前後に死ぬるもの多く、また、河原・白河・西の京、もろもろの辺地などを加へていはば、際限もあるべからず。いかにいはんや、七道諸国をや。
大飢饉による死体が京の都のあちこちに転がっていて、隆暁法院という僧が2ヶ月を費やしそれら全ての額に「阿」の文字を書いてまわった。そしてその数を数えたところ約42,300人に達し、京でだってその数を超えるだろうことはわかり切っているから、全国的にはいかほどの人がモノを食べられずに死んだことだろう、と長明は書いた
梵字である「阿」というのはアルファベットにおけるAではあるけれど、Aに意味がないのに対して阿には「根源(アルケー)」や「本質」といったような意味がある。42,300という数字は、ひとつの死体をいち、に、さんと積み上げて数えた数とはちょっと違い、死体ひとつ毎度まいど出会うその度に、始まりも終わりもない「根源」へといちいち還し、そして気がつけば辿り着いた「数」なのだ
ひとつの石を積めばふたつ目の石をその上に積みたくなるのが人間で、そういう感情の芽生えのその先に数学がある。だけれどそう石を積んでいった時に立ち戻るべく、始まりも終わりもない「(ゼロからではなく)ゼロまで」をココロのどこかに留めておくことが人間にとっては必要だ、と数学者の岡潔は言っていたのだと思うけれど、私には、僧が異臭たちこめる都において、阿字をそれこそ半ば機械的に書いているそのサマ(だけれど現代のわれわれには怪奇的にみえるそのサマ)に、そしてそのことを鴨長明が半ば放心的に文字を連ねているそのサマ(だけれど現代のわれわれには変質者的にみえるそのサマ)に、価値から離れた違う「なにか」があるような感じがしている
ただ、今はそう感じるだけで、その先の考えがあるわけではない
今年の冬は気味悪いくらいに暖かく、啓蟄の時期を待たずに、もうそこらを虫が飛んでいることがある
風が吹けばそれに春を感じるけれど、菜の花が勢い余って咲くことはまだないようで、そのことに少しほっとする。ほっとしているそのほっとした感じは、冬の、気味の悪い暖かさに端を発している。そうなのだとしたら、その、ほっとしているそのほっとした感じには、どんな価値があるのだろう。そして、冬を気味悪く感じるその感情には、どのような意味があるのだろう
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.019
「自分の魂に従って書いた文章は、そのまんま自分の魂のカタチをしているような気がする」と過去どこかに書いたけれど、その時は意図的にだったとはいえかなり大切なものをすっ飛ばしたので、『方丈記私記』の番外として書き加えておく。まず、言葉は社会制度であり、つまり言葉を使うその活動は個人の魂うんぬんというよりもむしろ共同体が採用した「制約の総体」(ツェランが言うところのいかがわしい言葉)として現れてくる。そのことは、SNSに広がる言説やそれらコメント欄でのヤリトリの数々を見ればわかるはずだ。ただ、いい置く必要もないほどトウゼンなことだと思うけれど、社会というのは世界(自然、地球、宇宙)の全体ではなくほんの一部であり、社会制度としての言葉もまた言葉全体のほんの一部だ
ひとが無意識的に宇宙とやらに接続している可能性は否定しないけれど、ピュシスの側がその身を隠してしまうのであれば、われわれの目に見えるのはやっぱりますます社会だけ、ということになる。そんな社会性にまみれた世の中で、言葉でもって言葉のことを書く難しさは、ある。それは、絵の具でもって絵の具について描くことが難しいこととは、ちょっとちがう難しさをはらんでいると言える
・・・・・・・・・・
2000年(平成12年)、エチオピアで260万年前の道具が発見された(出典:ナショナル・ジオグラフィック2015年1月)。このジジツから、少なく見積もっても300万年くらい前に人類は道具を使っていたと言うことができるそうだ(その後、2011年にはケニアで330万年前の道具が発見されたので半ばそれは立証されたと言える)。道具の使用者は、当初考えられていたホモ・ハビリス(器用な人)よりも50万年遡った人と猿の境にあるアウストラロピテクス・アフリカヌスである。彼らは、いわゆる猿人と呼ばれる初期の人類で、具体的にはその石器を使ってモノを割ったり、捕らえた獲物の肉を骨から剥がす、といった行為をしていたようだ。その石器の発見と、アウストラロピテクスの手の骨の内部の編目構造(道具を使っていないとそういう構造にならないらしい)により、それは証明された
道具の利用は、人類特有の生存技術と言えるだろう
そして、ご承知の通り技術というのものは進化する
アウストラロピテクスよりも300万年後に生きるわれわれの道具を使う技術、そして道具を造る技術(しいては道具を造るための道具を造る技術、道具を造るための道具を造るための道具を造る技術)は、それだけの歳月をかけてえんやこらとここまでやってきた。ひとが馬に乗るようになったのがいつからなのかわからないけれど、今ではほぼみなが馬ではなく、アクセルを踏めば簡単に100キロを超える乗用車に乗っている。車そのものの進化とともに、その燃料であるところのガソリンの精製技術もまた進化している。さらには水素や空気を燃料として走る車の話を聞いて久しい。科学は、「なんでこれはこうなの?」というココロの中の疑問とその研究の蓄積によってモタラサレたけど、その研究もしくは実験精度は、様々な道具の進化にともなって上がっていったことだろう。エジプト文明やメソポタミア文明からもさらに5,000年の時間を費やしてそのつど最新の道具を駆使し維新されていった現代文明における科学技術は、まさに目眩いがするくらいのところに到達した。そのことを、毎日の生活においてジッカンしたりする
それで、「言葉」の場合は、どうだろう
石が、空腹を満たす(狩りを成功させ、より多くの肉を骨から剥ぐ)ため、車が、少しでも先を急ぐために使われるそのかたわらで、言葉そのものは直接的な成果をもたらさない。それでも言葉は、他者とのコミュニケーションを図るための道具であり、他の道具や科学技術と等しく当初よりもかなりの進化を重ねて来たであろうことは、ソウゾウに難しくない。ただそうだとしても、
わたしは、ネアンデルタールのひと同士よりも、同じサピエンスであるはずのあなたと、うまく対話をしているだろうか?
われわれは、縄文人やネイティブアメリカンよりも、言葉による(宇宙)遊泳を、うまくやっているだろうか?
そう問うにつけ、やっぱり、なんだか頼りない気持ちになるのは、言葉が、花を見て隣のひとに「きれいだね」とつぶやくために使われたりするところからあまり離れていかないことと関係していて、つまり、車がガソリンを燃料とするように、言葉がココロをその燃料としつづける限りにおいて、言葉は、いつだってココロのありように左右されてしまうのだ。ココロが遺跡のような形では目に見えないためその進化の過程のいちいちを読み解くのは困難だけれど(参考:『心の先史時代』スティーヴン・ミズン)、どちらにしても、今、ココロの精製がうまくないのであれば、どれだけ道(ネット)が奇麗に舗装され張り巡らされていったとしても、言葉は、いつまでたってもがたごとぎくしゃく粗末なまま、その道を走っていくことになる
ひとの手による技術は、水平的な進化が許されている。方や、(ココロから発せられるところの)言葉の技術というのは、あくまでも垂直的な進化しか許されていない。つまり、言葉が、伝統やその時代の権威の厄介な担い手となってしまう傾向が強いのならなおのこと、その「古い言葉」に対抗するための「新しい言葉」というのは常にいつだって、わたし、において、その<最初>から発見、発明されていかなければならないのである
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.018
平成27年あたりから、益子の山本八幡宮で執り行われている「山本太々御神楽」を観察するようにその練習から映像におさめているけれど、来年あたり、自分も五行に参加させてもらおうかなぁ、と密かに企んでいる。仕事としては、今年でもう5年目になるけれど、ここに出口があるなんてことは最初から考えていない、すべて遊びの一環だ
(土器や土偶を作る時に限る話でもないと思うけれど)縄文人が、誰のものともつかないような意識でもって、時間も空間もない、いわゆる数を数え始める前のような場所に意識の一端を据え置いて生きていた可能性を先に述べたけれど、御神楽を観察するにつけて、鈴とお面は、数を数え始めてしまったわれわれが人為的に、そこ、つまり0(ゼロ)と仮定した場所へと意識を飛ばすために発明した道具だと思えてくる。鈴は、舞を舞っているひとの手に握られているから振動はそのまま演者を包むだろうし、うまいひとが鳴らした鈴は、うまいからこそ、誰が鳴らしても同じような鈴の音として場を満たす。決められた動きだからそれに連動してしゃんしゃんと、鈴は、いつの時代にあっても同じように震えてきたはずだ。そして、面を自身の顔に装着する行為こそ、演じている対象と主体との距離を限りなく0へと近づける直接的な助けとなったはずだ
数学者の岡潔が海外の数学者と対談した際に先方が「数学は0からが大事だ」と述べ、それに対して岡は「数学は0までが大事だ」と返答したという。0<から>をひたすらに積み上げてきた西欧のひとの意識のあり方に親しんで久しいわれわれは、あくまでも自立した個人として、どこかイタダキを目指して生きているようなところがあるし、そういう仕事にうっとりとすることも多いけれど、僕が文章を書いたり映像を撮るのはのはあくまでも0<まで>へと意識を飛ばすためである
建築の仕事をしておきならが恥ずかしいけれど、僕は、(自分のことも数字そのものも)恨むほどに数字というものが苦手だ。でも、0というものが仮定されていて、そしてそれが円でなく楕円であったジジツにだいぶ救われているようなところがあった。0が、ヨーロッパではなくインドで発明されたこととおそらくは無関係ではないと思うのだけれど、そうではなくって0が円の姿をしていたとしたら、数字は、ますます(僕にとっては)恐ろしいものと思えたはずである
寺尾紗穂さんの曲に『楕円の夢』というのがあって、ついこの間、エッセー『彗星の孤独』にその曲のことが書いてあったのを読んだ。その中に、花田清輝の『楕円幻想』からの引用があって、それをここでも引用してみたい
「いうまでもなく楕円は、焦点の位置次第で、無限に円に近づくこともできれば、直線に近づくこともできようが、その形がいかに変化しようとも、依然として、楕円が楕円である限り、それは、醒めながら眠り、眠りながら醒め、泣きながら笑い、笑いながら泣き、信じながら疑い、疑いながら信じることを意味する。これが曖昧であり、なにか有り得べからざるもののように思われ、しかも、みにくい印象を君にあたえるとすれば、それは君が、いまもなお、円の亡霊に憑かれているためであろう。」(出典:『復興期の精神』)
この、円、という箇所に、真理とか、正義とか、正しさとか、客観という言葉を当ててみるといいだろう。僕は、花田がそうしたように、寺尾さんがそう歌うように、これらの亡霊から逃げるようにして生きてきたし、これからもできるだけ不真面目に楕円の夢でだらだら遊んでいたいと思っているが、言い置く必要もないと思うけれど、楕円も円のひとつである。だから、僕の中にだって逃れられないようにしてある種の「正しさ」が潜んでいるわけで、ついてはせめていつだって、そのジジツを自覚していようと思う。御神楽の練習で、先輩が後輩に「動きは覚えていなくたって、鈴の音を追っていればシゼンとわかってくっから」と諭している場面に幾たびもでくわした。それは、鈴を操っている主体であるはずのひとが消えていることを前提にしたものの言い方だし、その時にわかってくる「正しさ」は、ピュシスが隠れることを好むのと同じようにきっと掴んだ側から溢れていって消えてしまうほどの儚いものだろう。いや、そもそも、岩のように硬く不動の「正しさ」なんて歴史を振り返ってみたって一度も存在しなかった。でも、0がまるでそこに存在しているかのようにひとが振る舞うのと同じことで、ひとは、岩のような固さの「正しさ」をどこかに在るもんだとしたいのか
「明るい道と暗い道 おんなじひとつの道だった あなたが教えてくれたんだ そんな曖昧がすべてだと」(寺尾紗穂『楕円の夢』)0だって、正しさだって、あくまでもぼうぼうとした意識で舞っているような瞬間に、鈴の音に紛れるようにしてほろりとわたしにやってくるようなものに違いないのに、、、。そんな曖昧がすべてなんだろう、この頃とくにそう思う
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.017
言語矛盾かも知れないしずいぶんな放言になる恐れもあるかもしれないけれど、万物の根源が「水」であるのか「火」であるのかというその「根源」もしくは「根拠」について、実は、タレスもヘラクレイトスもそれほど執着していなかったような気がする。むしろ、火に当てられ水を沸かすことを可能とする「器」であるところの「万物の~」と言うその時の<感覚>もしくは<意識>の発露にこそ、彼らはこだわったのではないだろうか。だからこそ「万物の根源は数字である」と言い、根源(アルケー)であるところの数字の方に執着したピタゴラスに対してヘラクレイトスは烈火の如く怒ったのだと思う。そして、その器であるところの<感覚>なり<意識>というものの「深さ」がベースとしてわれわれに備わっていることは確かなジジツで、なぜなら、タレスでもヘラクレイトスでも誰でもいいけれど「万物の~」と言うことが可能となった瞬間に語られる「万物」という意識の中には、わたしもあなたも、土も木も風も、虫も粘菌類も、爬虫類もシダ植物も細菌も、全部がぜんぶ含まれているからである。その意識が存在する場所では時間も空間も無化されているから、つまり、2500年前にタレスやヘラクレイトスが「万物の~」と語ったその瞬間の彼らとわれわれはまさに垂直的に「万物」の中にあって、あっちからこっちという指向性もなくまるっと一緒くたになっているのだ。そして、その意識の中で全てのものがまるっと存在する場所のことを、時に、われわれは「誰のものでもない場所」とか「何処にもない場所」とか、はたまた「ユー・トピア」と言ってきた
「文学は、自らそれが何であるのかを言うことはできません。ただ繰り返し繰り返し千年以上にわたって自らをいかがわしい言葉に対するアンチテーゼ、と見放してきました。実生活はいかがわしい言葉しか持っていないからです。ですから文学はそれに対して言葉のユートピアを対置させてきたのです。この文学は、たとえそれがどんな時代とそのいかがわしい言葉に準拠しているとしても、絶望しながらこの言葉に向かって歩いてきたが故に讃えられるのであり、人々の誇り、希望となるのです(中略)その予感された言葉に向かう方向としての文学を書き続けなければならない」
こう語ったのは、自らはルーマニアの強制労働所をかろうじて生きのびたけれど両親をドイツの強制収容所で失った世紀の詩人、パウル・ツェランそのひとである。ツェランは、戦後においてもなおはびこっていた反ユダヤ主義的雰囲気の中で、誰のものでもなく何処にもなく境界のない世界に、詩、でもって向かっていった
ユダヤ人であるツェランと意識を共にした数少ないひとのなかに、オーストリア人であるインゲボルグ・バッハマンという詩人がいた。このふたりの間で交わされた書簡が、今に生きるわれわれには痕跡として残されている。ふたりは、古い言語がつくった境界(時代)を突破するための「新しい言葉」を、新しい意識でもって触れられる「場所」を、戦後の世界に共に求めた。時に励まし合いながらユートピアの光の中で詩作を通して生涯その実践をし続けた
第二次世界大戦の傷跡が残る占領下のウィーンで出会い、そして互いに愛し合うようになるまでにはたいして時間がかからなかっただろう、その納まり方は、まったくもってシゼンなはずだった。しかし、ツェランは、新しい世界の新しい言葉を探すよりもその遥か前に、古い言葉によって、制約の総体としての言葉によって深い傷を負ってしまっていた。彼の心と身体には、深々と古い傷が刻まれていた。そしてその傷は、ツェランを古い世界に束縛し続けるには十分すぎるくらいの、静まらない、鈍い痛みとなってずっとずっとそこに在り続けた。男であるのか女であるのか、ユダヤ人であるのかドイツ人でるあるのか、ヨーロッパなのかアジアなのか、家庭があるのか独り身なのか、傷を負っているのかむしろ時代の恩恵を受けているのか、つまりそういった世界を分かつもの、断つもの、境界、世界を分断するその溝に、穴に、終始オトコはトラワレ続けた
自分がナチス党員の娘として不自由なく生まれ育ってきたというジジツもまたツェランを苦しめていることを知っていたバッハマンは、詩人として結局のところ言葉では超えることができないものがあるという行き詰まりにあった男を、けれども辛抱強くこう励まし続けた「さぁ、私たちは(新しい)言葉を見つけましょう!」と。そして、深く包むような眼差しでもって、愛、にもまた新しいカタチがあることを男に示し続けた。男が死んでからもいっそう頻繁に、さらに切実に、、、
ツェランは1970年(昭和45年)に、水によって死に(入水自殺)、後を追うようにバッハマンはその3年後の1973年に、火によって死んだ(寝たばこによる重度の火傷)。物理的に火と水は出会わない。それと同じように男と女はシゼン現象そのまま、互い、はじきはじかれてこの世界から消えていき、消えていったその先でも交わらずにいるのだろうか?
ツェランとバッハマン、そしてバッハマンとツェランの妻との間で交わされた書簡が『バッハマン/ツェラン往復書簡 心の時』(青土社)としてまとめられていることは先に書いた。600ページに迫る大著だけれど、この本には、ツェランとバッハマンとの距離、ツェランとツェランの妻との距離がそのまま、もう、触れられぬ、という痛みとして、残されている。世の中のひとに「ひと」が見えるのは(むしろひとばかりがみえるのは)自分とひととの間に距離があるからだけれど、ツェランが死に、バッハマンが死んで距離が失しなわれて、それでも、いや、だからこそ、そこに(本の中に)愛だけがぽつねんとあるのが、わかる。その微かなぬくもりが読後の「わたし」に広がってくる。数々の詩や優れた文学を世に送り出した彼らだけれど、ふたりにしてみては、「新しい言葉」というものをついぞソウゾウすることが出来ず失意の中に死んでいった、ということになるなのかも知れない。しかし、この、行ったり来たりした意識の痕跡としての文学に、「男の意識」と「女の意識」はたまた「ユダヤの意識」と「それ以外の民族の意識」という制限をゆうゆうと超えていっているそのサマがぼわぼわと滲んで見える。そして、ふらふらと世界の全体がにょろにょろと顔をのぞかしているのがカンジトレル。隠れたはずのピュシスが、彼らが見失った愛が、今、ここに、ほら、と顔をのぞかしているようである。そして、本を閉じると、バッハマンがツェランに、さあ、と促し続けた言葉がそのまま今に生きるわれわれを促す言葉として、ぼーぼーと聴こえくるようである「われわれは、われわれの時代の(新しい)言葉を見つけましょう!」と
そう、私には、聴こえる
そう聴こえると思うのは、ややロマンチックに過ぎるのかもしれない。だけれど、彼らが死んで触れられるものとしての存在から離れていったその場所がわれわれにはすっぽりと隠されているのであるから、彼らが今、ふたり、水となり火となってそれでもなお寄り添っている、という風に考えることもできるし、考えないでいることもできる、ということなのだ。「同じ河にわれわれは入ってくのでもあり、入っていかないのでもある、存在するのでもあり、存在しないのでもある」ヘラクレイトスは2500年前にそう言った。そして、その1700年後に、同じ(ような)河の流れを見ながら鴨長明は、自分の渇望を断ち切るために出家した。ひとはひとの権力に対する執着を汚ならしいものを見るみたいに見るし、そのくせ彼のようなひとのことを敗北者とらくらくと烙印を押す。けれども、そんな烙印を押された彼はひょうひょうと、誰のものでもない場所をただただ誰の意識でもない意識で見ようとしていただけなのかもしれない、と、わたし、なんかは思ったりする
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.016
紀元前500年前にヘラクレイトスが「万物の根源は火である」と言うそのさらに前に、タレスという人が「万物の根源は水である」と言ったそうだ。ヘラクレイトスはタレスの死後に生を受けているから両者が言葉を交わしたことはないはずなのだけれど、こうやって並べて記述されたそのとたんに「場」が生成され、まるで彼らが言葉を交わしているように思えるから不思議である
万物の根源を火に見たヘラクレイトスは、こんなことも言っていたようだ、「ピュシス(自然)は隠れることを好む」と
ピュシスは(好まれて)隠れているということで目にも見えないから手に負えず、けれども「それ」が目に見えてくるのを待って「そこ」に留まるのも退屈だから、とわれわれは待つのを止め「そこ」から新大陸を求めるように勇んでススンできた。そして今に至る道を選んだわけだけれど、選んだ道の先にあったのがロゴス(理性)だったのか、観念主義だったのか、主観主義だったのか、経験主義だったのか、実存主義だったのか、近代主義だったのか、そんなことに私はあまり興味がなくって、長いなっがい道程を振り返りながらもわれわれの遥か後ろにおいて置かれた「そこ」こそが今たまらなく気になっている
私が住む森の中で、たまたま木が倒れる瞬間に立ち会ったことがある。特に風が強かったわけでも、湿った雪が枝葉に積もっていたわけでもなかった。一見して特に外因があって倒れたわけでもないその木は、人間の年齢でいうと幾つくらいになったのだろう、他の木の影に入るような幼木ではなかったし死に絶える直前の老木でもなかった。いつだって倒れる可能性はあったにしてもその時に限って倒れる理由などあったようには見えなかった。何年も風雨に耐えてきて、それは、私には見えないタイミングを待って、倒れた
ピュシスが隠れることを好むのなら、人間の私にはピュシスは「死」を隠しているように思えてくる。だってジッサイに人間として生きるわれわれはだれひとりとして死を、死ぬというコトを知らないのだから
またしても映画の話になる。人の、生きていることと死んでいることの境、その境に流れる川をただ静かに見つめるような『眠る男』という映画が平成8年に公開された。映画の主人公である眠る男タクジは文字通り植物のように寝て横たわったままである。私が森の中で見た木は倒れただけで死んだわけではなかったわけだけれど、それと同じことで、タクジもまた寝たままに生き続けている。映画の冒頭部のシーン、水平に眠るタクジという男のすぐ上に、花をつけた白梅ととても大きな満月がぽっかりと浮かんでいる。ひとはこんなにも自然物と近いのだよ、と観ている者はそのジジツを優しく伝えられる。眠る男の眠る部屋、いや、ルームと呼ぶにはかなり躊躇ってしまう、ただ「場」と名指すしかないその場所に扉や窓はひとつもついていない。限られたものと限りないものとの境としてではなく、限りないものと限りないものとの境としての身体が、扉としてある。しかもその扉は、目や鼻や口などの感覚器官がそうであるように、つねに外部に対して開け放たれている。タクジの耳はずっとずっと自然の音を聞いていて、タクジの鼻はずっとずっとその匂いを嗅いでいる。映画の始めから終わりまで絶え間なく川の流れる音が聞こえていたような気になるほど、画面に水がゆき渡っている。そして、私は、というと、それら一切合切をタクジと共有したのだ、と映画が終わり、音が途絶えてから知る。映画を観ている私こそがタクジだったのだ、という気すらしてくるのだったけれど、でも、そういったことですら、つまり川の流れる音を聞いたりそれらから何かを想起したりすることすべてが動物である「人間」のすることだ、ということにしみじみと行き当たる。私は確かにタクジ(自然物)だ、でも、私はタクジ(植物)ではないのだ。映画は、私を突き放すようにして動物である「わたし」にとどまるよう呼びかけているようでもある
われわれは、タレスやヘラクレイトスの時代からいち、に、さんと数えられる歴史の時間よりももっともっと長い時の間、動物であることを結局はやめたりはしなかった
(好まれて)隠れたピュシスがでもいつでも「そこ」にあることを、タレスやヘラクレイトスは動物であるところの「身」をもって知っていた。いや、われわれだって動物であるところの「身」をもっているわけだから本当は「そこ」にあることを知っているはずなのだけれど、彼らとわれわれとの間に深い溝があるとすれば、それは、知っている、というそのことを彼らがいっときも忘れることがなかったのに対して、われわれの方と言えばもうずっと長いこと(生命の歴史から考えればほんの束の間なんだけれども)、その知っている、ということをすっかり忘れてしまって「ここ」にある、というジジツに違いない。そもそも万物の根源へと遡行するその意識が万物に包まれていることを知っていなければ、「万物の~」と言いはじめることなど出来ないはずで、「万物の根源はエネルギーである」とわれわれが言う時に、われわれは、それをジッサイには「考えて」もいないしましてや「感じても」いない。つまり「万物の~」と語り始めて何かを知ったようなフリをするわれわれの「身」は万物の側にあるのではなく、あくまでも「わたし」という主体の側にある。そして、わたしが主体の側にあるというそのことに関しては、なぜだか熱に浮かされたように強く主張し、そして、信じて疑わないのだ
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.015
15年近く前のプロジェクトがカナダの美術館CCA(Canadian Centre of Architecture)で展示されることになった。もはや同じ人間(私)がやったプロジェクトとは思えないのでかなりに他人事なのだが、平成が終わり令和となって美術館に仕事を提供することが続くその事実が不思議なことに思える
スイスに住むステファン・ブルナーと、フランスに住む写真家のクリスチャン・ノールとの協同で「KOBAN PROJECT」なるものをやったのは、確か平成17年くらいだったと思う。同じ「交番」という果たさなければいけない設計要項に各建築家がどのように応えているのか、ということを観察したり当の建築家に聞いてまわった覚えがうっすらとある
カナダの美術館がどのような観点でこのプロジェクトを取り上げるのかはあんまりわかっていないのだが、オファーにはスーパーキャピタリズムとかハッピーライフという言葉があるので、超資本主義社会における幸せを建築的に模索し展示しようとしているでしょうか。レヴィ・ストロースもロラン・バルトもそうだったけれど、海外の人は日本に来て日本の社会の納まりかた?一見カオスだけれども秩序だっているそのバランスに「うんうん」と変に納得しちゃうところがあるが、でもやっぱり内実はちっとも納まっていないことの方が多いと思うのが、ここに住む人のジッカンかもしれない
平成17年当時と比べても日本はますます監視社会になっていて、平成26年には特定秘密保護法、平成29年にはテロ等組織犯罪準備罪が成立するなど危うい法案がいくつも通った。なにが危ういかと言うと、その法案を通した人が演説でやじられて、やじった人を「こんなひとたち」それで応援してくれる人を「私たち」と安易に線引きしてしまうことに全てアラワレテいる
ただそんな方が声たからかに謳う「エブリシング is アンダーコントロール」という言葉の呪いの強さはなかなか否定することはできない。なぜなら、そう思っていないと精神が崩壊してしまう人が多数いるのも事実だし、そういう言葉で奮い立っていないと回らないような社会であるのも一部ジジツなのでしょうから。では、その呪文に変わる豊かな言葉を産むような人がいるかと言うと、、、いや、私の廻りには、沢山いるのだが、ただ、結局、外からのそういう言葉に一喜一憂しているあいだは人はやっぱりハッピーライフを送れない可能性が高く、かといって、いつまでも自分の内側から湧いてくる言葉を待っているのもまた、とても疲れる。例えばあのサッカー選手(本田圭介)につぶやいた「リトルホンダ」のように内なる声がいつでも間違わず道を示してくれるわけではないですから
ですのでハッピーライフの源泉は、外側でもなく内側でもないところにあるのだろう、と思うけれど、それではそれがどこかというと、きっと外側とか内側とかって言う概念がないところ、ってことになる。そして、芸術家や映像作家と呼ばれる人は、そこに触れるための努力をすることが仕事なんだと思う。外側って概念も内側って概念も人が造ったものなのですから、それを壊すのもまた人でなければならない
それで、平成生まれの田中彰さんとか居相大輝さんみたいな若い人と仕事をするととってもびっくりするのは、そもそもにその概念(に捕われている感じ)がとっても薄いということ。今度の『えごのき縁起』で起こっている展示もまた、大きいとか小さいとか、内側とか外側っていうことをぴょんとひとまたぎで飛び出しちゃっている
交番は、外側となる社会の適所に配置されることで結界を造るようにして内側を造るって行為なんだろうけれど、田中さんのような優れた作家は、もう最初っから包まれた存在でありながらあらゆるものを包んでいる。そう、ウォルト・ホイットマンの言うように「わたしは大きく、多くのものを抱合する」その人は、でも当たり前だけれどそも大きなものに包まれているわけなのだ
そんな状態で彼が名指す「私たち」って、どんだけ広いんだろう、と思う
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.014
2018年の暮れに近い頃、私の関わるドライブイン茂木という場所でふたつのイベントが行われた。一つは『草のほほ』と名付けられた居相大輝さんの衣の展示(pejiteとの共同開催)、もう一つは『北風と太陽』と名付けられた河合悠さんのパフォーマンス。前者では、まぶしいばかりの光が満ち、文字通り自然と人とがほぼ等しくその日の光の中で戯れている、そんな景色が広がった。後者には、遊びほうけた子供が「いっしょにやろうよ」とまだ燻っている遊び心にまかせて薪で火を焚き暗闇で悪ふざけをしている、そんなおかしさがあった
「この世界は、神にせよ人にせよ、これは誰が作ったものでもない。むしろそれは永遠に生きる火として、決まっただけ燃え、決まっただけ消えながら、常にあったし、あるし、またあるであろう。万物は火の交換物であり、火は万物の交換物である」
こう主張したのは「万物の根源は火である」と説いた紀元前500年頃に生きた人、ヘラクレイトスである。ヘラクレイトスが言うように、わたしもあなたも火を根源としている。そして、わたしとあなたは絶えずなにかを交換している。わたしと自然は、と言ってもいいと思う。宇宙がたった一回のビックバンから出来たとすることや、エネルギーの保存の法則(エネルギーが運動エネルギー、音エネルギー、熱エネルギーなどに移り変わっても、エネルギーの量は不変であるとする法則)のことを考えると、うんうん、とうなずくばかりである。例えば、平成最後の年末に光りに溶け込むようにして『草のほほ』が執り行われ、闇に紛れるように『北風と太陽』が起きたそのふたつの出来事も、けっして誰かが作ったものではなかったし、まるで手渡しで交換されたかのごとくわれわれの前に差し出された。そして、なによりもその両者に指差せるような境界線は存在しなかった。それらは、重なり、転び、こぼれ、にじむように結ばれていた。エネルギーと呼ぶしかないような「なにか」がその場で生成されていた。かと思えば次の瞬間、こちらの意志とは関係なくあっさり消滅していった、いや、なにかにトッテカワラレテイクのを感じた
振り返って、やっぱり火だけが常にそこにあったように思う(つまりは、闇も常にそこにあったということ)。光と闇がもつれるようにして交換されているその姿を、われわれは目にした。仮に、光と闇のその境を私に指差して示す者がいたとしても、きっと指差されたその場所はある人には十分にまぶしく映え、またある人にはすっかり暗さに落ちきって見えないはずだ。どちらにしても万物はあっちからこっちへ、こっちからあっちへと絶え間なく流転している
この世界に存在するすべてのものは一瞬たりとも静止していることはなく、絶えず生成と消滅を繰り返している、そう主張したのは鴨長明であり、ヘラクレイトスであった。ヘラクレイトスは、鴨長明と同じく世間が疎ましく感じられた人のひとりで、人里離れた山に暮らしの元を築き、草や木の実を食べて過ごしながら森羅万象に心を割いた人だった
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.013
さらさらと解説できるような事件ではないけれどひとまず「地下鉄サリン事件」の概略だけを追ってみる。私がちょうど成人をした平成7年の3月20日に起きたこの事件は化学兵器を使用した無差別テロで、駅員を含めて死者13人と5,800人を超える負傷者数を出した。歴史上のあらゆる事例と比べても際立って異質な事件が東京のど真ん中で起こったのだから、その時の混乱ぶりはソウトウなものだった。事件のほぼ一ヶ月前に起きた(私の祖母も生き埋めになった)阪神淡路大震災の騒ぎが一瞬で吹き飛んだ。特に阪神淡路から距離の離れた東側のメディアは、よりスペクタルな地下鉄サリン事件の報道に偏たり、視聴者もそれを好んだ。それはそれで問題だけれどもとりあえずは仕方がないことだとして、しかし、いつまでたっても焦点が当てられるのは事件の「異質さ」だけだった。われわれは「至極当たり前な」ふたつのことを努めて、しかも迅速に忘れようとした。それは今もなお複雑化に拍車をかけている地下鉄を舞台とした事件であったということで、被害者は、わたしやあなたであった可能性が多分にあったということを、そして、社会に行き場を失った若者の受け皿として機能した宗教団体が起こした事件ということで、加害者は、わたしやあなたであった可能性が多分にあったということを
村上春樹が書いた「アンダーグラウンド」という本がある。本書は、村上本人が地下鉄サリン事件の被害者をインタビューして書き起こした内容のもので、700ページを超える大著だ。既にジュウニブンに国民的な作家であった村上がこの本を書くに至った動機はあとがきに詳しく書いてある
「もしあなたが自我を失えば、そこであなたは自分という一貫した物語をも喪失してしまう。しかし人は、物語なしに長く生きていくことはできない。物語というものは、あなたがあなたを取り囲み限定する倫理的制度を超越し、他者と共時体験を行うための重要な秘密の鍵であり、安全弁なのだから。(中略)しかしあなたは、というか人は誰も、固有の自我というものを持たずして、固有の物語を作りだすことはできない。エンジンなしに車を作ることができないのと同じことだ。物理的実体のないところに影がないのと同じことだ。ところがあなたは今、誰か別の人間に自我を譲り渡してしまっている。あなたはそこで、いったいどうすればいいのだろう?あなたはその場合、他者から、自我を譲渡したその誰かから、新しい物語を受領することになる。実体を譲りわたしたのだから、その代償として、影を与えられる。あなたの自我が他者の自我にいったん同化してしまえば、あなたの物語も、他者の自我の生み出す物語の文脈に同化せざるを得ない。(中略)そういう観点からすれば麻原は、現在という空気を掴んだ希有な語り手だったかもしれない。彼は自分の中にあるアイデアやイメージがジャンクであるという認識を恐れなかった。彼はまわりにあるジャンクの部品を積極的にひっかきあつめて、そこにひとつの流れを作り出すことができた。」
そう、麻原彰晃は、「今を生きる同時代の人間」に気前よくそして説得力をもって物語を差し出したひとりの優れたストーリーテラーだったのだ。冷静になった今、われわれにはその物語に乗っかった人間を、つまりはあっち側の人間をこっち側にいながら、馬鹿だ、と嘲笑することが簡単にできるだろう。けれども、であれば、われわれの側に(つまりこっち側の人間に)、あなたやわたしをこの世界に繋ぎとめておくための豊かな物語を差し出すことに成功している人が、何人いるであろう?
この問いは、村上に限らず言葉でモノガタリらしきものをつくる作家に付いて回る。「追いつめられると、時間と空間に関する考察しかなくなってしまうでしょう。すると、小説にとってストーリーはなんなのかということになる。」東日本大震災の起こった平成23年に、古井由吉は対談でそう語っている。<今に生きる>あなたとわたしをわれわれとして繋ぎとめておいてくれる物語とは、いったいどんなスガタカタチをしているものなのか?そもそも、わたしやあなたが使う言葉はイマ、われわれをどう囲っているのだろう?囲われたその場所は、固いのか、柔らかいのか、霞んでいるのか、ザルなのか、恐ろしいのか、親和性に富んでいるのか、、、。この問いは、映画『ハトを、飛ばす』を撮っている時もそうだったし、短編『土と土が出会うところ』を執筆するさなか、映画『方丈記』を撮るさなかにも、私に、繰り返し迫ってきている
「キリスト教」であれ「ディズニー」であれ「古事記」であれ、それらモノガタリと呼ばれるものは、わたしとあなたは同じようなココロをもった「われわれ」の一員なのですよ、そういうことを認識する上で作り上げられた共同幻想であり、その大きな物語にトモニ含まれることを生きる上での「安全弁」としたことは、おそらくはジジツだろう。われわれホモサピエンスがどんな時代にも物語をクリカエシクリカエシ語ってきたことは、屈強な身体を持ったネアンデルタール人を含めてあまた多くの人類が滅んでいくなかで生き抜くための戦略だったはず。そして、その物語を語るための言葉は、そのためにこそ発展してきたとさえ私には思われるけれど、7万年という歳月をかけて積み上げてきたはずの言葉が囲う「われわれ」は、これからも帝国的で宗教団体のようなスガタカタチをするしかないのだろうか?
今年、忘れたいとばかりに地下鉄サリン事件を企画した幹部や実行犯の死刑が(新証拠が提出された上での再審が協議されていた死刑囚も含めて)執行された。彼らが何に恐れ、何に行き詰まり、何に希望を持ったのか、それらを語る言葉は(彼らが執筆したいくつかの本を除いて)もうこの世には存在しなくなることになる。永遠に使い続けられるエネルギーという夢のような原子力の平和利用がただの子供がつくような嘘であったことが東日本大震災で身にしみてわかり、そのぽっかりと空いてしまった空き地を埋めるべく2020年には「アンダーコントロール」と叫ばれつつ東京オリンピックが開催される。さらにその先には建築界のオリンピックである大阪万博が2025年にあり、それらの代償として与えられる影が私の住む世界をどんより覆う
言葉を道具として使いながら生活をしている私がどれくらいストーリーということを考えているのか、やれているのか、と改めて身につまされる思いがしている
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.012
7月7日の七夕の日、西の地域を中心にして歴史的な豪雨が降った。もうこの災害に名前らしきものが付いているのかはわからないけれど、死者の数が200を 超えたのだからこれは立派な大災害だ。そして、同じ日に、政府は地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教の麻原彰晃を含めた複数人の死刑を執行した。9月 に入り台風21号が西日本を襲った。大型のトラックが吹き飛ばされ、電信柱がぼきぼきと倒れた。各自手にしたスマートフォンで撮影されたその映像が、も う、次の日には遠い私のところにも届く。そして間を置かずして北海道に震度7の地震があった。この、慌ただしい同時多発的な出来事を前に、方丈記私記を書 いている私は、間に合わない、という思いになっている。これだけのことが起き続けていたら、もしかしたら、平成の30年を綴るのに同じ年月の時間が必要な のかもしれない、とすら思う。友人の無事を想うその時に、もう次の災害が起きている
今朝、北米のハイダ族に伝わる神話がわたしの耳に入ってきた。朝から不機嫌に泣き叫ぶ子供に、朗読をして聞かせようと手にした本に載っていた
北米大陸をつくったワタリガラスが叔父のガーラン・クンと口論し、その叔父の怒りが洪水を引き起こした。世界をさらった洪水に生き残るものはいなかったけ れど、ほどなくして海から人間が生まれた。さらには、うたかた(泡)の女であるフォーム・ウーマンも現れた。当時、島々はまだ海の下にあって、岩だけが海 から顔をのぞかせていた。そこを宿り木にしようとしていた精霊たちは、けれどもフォーム・ウーマンを恐れて、海から上がることが出来なかった
うたかたの女は、ワタリガラスの精霊を生む者でもあった。最初の子供を産んだ時に吹いたうたかたによって二度目の洪水が起きた
母親であるフォーム・ウーマンは、こう言った、「お前達が偉大な何かを畏れたとき、乾いた土地をみるだろう」と。こうして、偉大な何かを畏れる気持ちをもったわれわれは、大地に住むことを許された(ハイダに伝わる創世神話の要約)
科学が発達したことによって、われわれは、かつて見えなかったものを見ることができるようになった。そのことはいつも強調されるけれど、かつて見えていた ものが見えなくなったことについて、われわれは、語らない。多くのものが見えるようになって世界は狭くなり、われわれは、畏れる気持ちをぽとりぽとりとトリコボシテいった。けれど、見えないものが増えていっていることを潜在的にはジッカンもしているから、われわれは、恐れをひとつひとつ拾い集めるようにして内部を脹らませていっている。恐れは、畏れと入れ替わるようにしてわれわれに忍び込む
恐れる人は、ひとりで居るのが怖いから党派を組む。党派を組む者は、自分と意見が合わない人を排除しようとする。それは、まさしく全体主義の姿をしている。今の政権を声たからかに攻撃する者の一部は、ほとんど写し鏡として、そんな政権と似たような党派を組んでいたりする。逆に、今でも偉大な何かを畏れる人は、世界の全体に対して感度を働かせられるよう注意を払う。全体に対して開いて待つ者は、鳥の声、虫の声、山の声、海の声、それぞれに対して聴く耳を持つ者だ。「全体性」と「全体主義」はとても近しい関係にある。それは、歴史が証明している。畏れは、恐れに転びやすいのだから仕方がない。けれども、恐れる必要がないことを知り、そして、静かに畏れること学べば、われわれは、乾いた大地に住むことをまた許されるはずだ
くどいようだけれど、「そう大地/神が言っている」と他者に対して声を出して言うことは、全体主義の津波を起こすトリガーを引く行為となりうる。「そう大地/精霊が言っているかもしれない」とひとり静かにその声を待てる者は、全体性に抱かれる
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.011
平成11年に封切られた『永遠と一日』というギリシャ映画がある。映画は、もう死期が近い老人が老人自身もそれを自覚しているので「明日、旅立つ」と言って飼っていた犬を引き取ってくれる人を捜しに出かける「今日」という日の物語だ。最初に頼った先の娘にはあっさりそれを断られ、さらにその夫から、老人の記憶の中で燦然と輝く「海辺の家」が売り出され明日にでも解体される旨をぶっきらぼうに伝えられる。老人は、失意の中に街を彷徨い、そして、車の窓拭きを生業とする少年に出会う。違法な移民を取り締まる警察から追いかけられているところ、さらには裏の組織に身売りされそうになるところを二度に渡って救う。しかし、少年は身寄りのない移民。一度、二度、救ったところで救ったことにならないという事実がどうしようもなく老人の目の前に、そして映画を見る者の前に曝されることになる。少年は、何万もいるそんな少年のうちのひとりである。「明日」という時間を照らさないどんずまりな空気が横たわり、ヨーロッパの歴史の始まりに位置するようなギリシャという国の道を塞いでいる。「今日」触れることの叶わない「明日」という時間が繰り返し語られている。と同時に、「今日」触れることの叶わない「過去」という時間が繰り返し脳裏に蘇る。明日には旅立つことを主張する老人、その老人の研究対象だった歴史上の詩人の言葉がつらつらと朗読され、明日解体される建物で、かつて娘の生誕を祝う華やかなパーティが行われている記憶が色鮮やかに再現される。過去は、まるですぐそこで起こっているかのごとく、辛く、切なく、淡く、美しく映し出され、明日は、一歩寄せては二歩退いていくような遠さに常にあり、険しく、過酷で、けれども希望とでも呼べるなにかがぽとりそこに置かれている気はする
知らず、生まれ死ぬる人、何方より来たりし、何方へか去る。また、知らず、仮の宿り、誰が為にか心を悩まし、何によりてか眼を喜ばしむる。
老人は、少年を家まで送り届けようとするけれど、国境だと思えるところに辿り着くやいなや、家は、フルサトごとかすみに消える。フルサトも家も幻であれば、少年は、どこから来たというのだろう。鳥に種を運ばれ発芽した植物でもあるまいし、人なのであるからには人としての彼なりの始まり方があったはずである。かたや、立派な家と恥じる必要のない名声を持ち、歴史の一部として歴史を繋いできた(と思っていた)老人は、死期を迎えこれからどこへ還るというのだろうか?いや、少年や老人に限らず、われわれは、どこからきて、そしてどこへとゆくのだろう。遠いとおい過去、きっとネアンデルタールの頃から変わらずそっくりそのまま今に至まで、この問は、われわれの胸にある
東日本大震災があって、私は、被災地を巡る旅に出た。そこかしこに遺体があったことを示すピンク色のりぼんがぱたぱたとはためいていた。いち、にー、さん、と数を数え始めてすぐに数はワカラナさに消えていった。そして、どうしてわれわれはこの世に生まれてきたのか、という問が、ぱたぱたと風にはためくりぼんに出くわす度に、おーい、という声と共にどこからかぷかぷかと浮んでくる。ワカラナくなった数に引っ張られるように、わたしは、さらに深く、ワカラナくなる
その主(あるじ)と栖(すみか)と、無常を争ふさま、いはば朝顔の露に異らず。或(あるい)は露落ちて、花残れり。残るといへども、朝日に枯れぬ。或は花しぼみて、露なほ消えず。消えずといへども、夕べを待つ事なし。
長明は、花(家)はいつだって枯れ、露(人)は夕べを待たずに蒸発するものだと言った。そして、その枯れた花びら、蒸発した露がどこへと消えるのかということはワカラナイと匙を投げた。波に攫われて、新築の家も古い家屋もほとんど等しく強固な基礎からざざざ引きはがされどどどとどどと陸へ沖へと押しやられた。私は、微かに残る痕跡を前にして、かれらがどこへと往ったのか、過去に生きた何万何億という人と同じように、さっぱりワカラナいでいる。そう、わたしは、ワカラナいさなかにいる。映画の中の少年や老人、あちらこちらの被災者、移民、難民、平和にぽーっとした人、きびきび働く人、みんな、明日どこへ還るのかワカラナイといういうことで、時、を同じくしている。仮の宿りと知りながらその都度その都度に家を求め、なんとか人を喜ばせようとする、ということで、場所、を同じくしている。不確かな明日、幻想としての過去は、今日という同じ円のなかでぐるぐるとまわり続けている。そうして、われわれは、いつだってワカラナいさなかにいる
きっと、いつでもワカラナいさなかにいるのが、人(人類)なんだ、と私は思う。ワカラナいながらもわれわれは、今という時、今という場所から過去へ未来へ思考を飛ばす、なんどもなんどもあっちへ往ってこっちへ還ってを繰り返しながら
映画の最後、老人は、一緒にいてくれ、と少年に懇願する。けれども少年は、明日がきたら旅立つ、と老人にはっきり別れを告げる。老人もそれを受け入れる。もしかしたら少年の眼には色鮮やかな明日がきらきらと光って映っているのかもしれない、と、私もそれを受け入れる。いや、あくまでもそう思いたい私が、今、ここにいるだけなのだろうけれど、、、、、
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.010
ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。
鴨長明の名前を知らない者でも、彼が書いた『方丈記』という随筆の題名を知らない者でも、日本人であればもしかしたらこの言の調べを一度は耳にした事があるのではないか。そしてこれはまだ『方丈記』の冒頭で、であるが故に読み始めに満足感がさらりと高まり実際に本を読み進めてみた、という人は少ないのかもしれない。斯く言う私も『方丈記』を映像にしたいと10年以上も前に思っていたのにもかかわらず、それを通読したのは『益子方丈記』という短編映画を撮った今から2年くらい前のことである。そんなイイカゲンな私が、なんで「方丈記私記」なるものを書いているのか書く側から恥を曝け出しているようだけれど、今はまだ筆が止まる気配がないから書き続けてみたいと思っている
16万の避難民のうち半分以上のおよそ11万の人がもと住んだ福島の土地へと還っていったと書いた。逆の書き方をしてみると、5万の人が7年経った今もフルサトへと還ることができないでいる、ということになる。さらに言うと、ゲンパツが爆発して指定された避難指示区域に住んでいた8万の人のうち、帰宅困難区域と指定されもはや還る見込みがなくなった2万を超える人は、結果、避難先で「安定した住まいを得ている」とされ、還れない5万というい人の数には含まないのだそうだ(NHKデータナビより)
少し詳しい数字を経済産業省のHPから引いて書く。南相馬に2人、富岡に3,953人、大熊に10,599人、双葉に6,142人、浪江に3,118人、葛尾に116人、飯館に257人の合計24,187の数の人は今、新しい場所で「安定した住まい」を得たことになって、生活をしている
建築の仕事を始めてなんだかんだ20年近くが経つ。大学を卒業した当初と較べると、現在の建築の仕様はかなり様変わりした。束基礎や布基礎が当たり前だった時代は過ぎ、今では地面を水平に覆うベタ基礎が住宅でも標準となった。部材と部材を繋ぐ金物の数は年々増え、気密はますます当たり前に求められるようになっている。確かに、今建つ家を見ていると、明日、風が吹いて倒れてしまうような家でない事はれっきとした事実のように思える。いや、しかし、と書くことには私にだってためらう気持ちはある。けれども、ここ数年に限って考えてみても、強固に建てた家が結果として、流され、燃え、壊れ、(人為的に)壊されることばかりが目につくのだから、いや、しかし、という気持ちにもなるのはそれなりに自然のことだと個人的には思う。311の被害は益子でも生々しかったけれど、そのほぼちょうど一年後、私の家の表通りを竜巻がぐごごごごと物をまき散らしながら過ぎていった。そう、本当にそれは一瞬のことだった。長明は、治承の辻風を見聞きして、「かの地獄の業の風なりとも、かばかりにこそはとぞおぼゆる」(地獄の業の風もここまで吹くことはないだろう)と書いている。人の家の駐車場がそのまま畑の真ん中に飛ばされひっくり返り、家や車のガラスがこなごなに割れ、ねじり倒されたケヤキに押しつぶされた家も散見できた。私の家は逆に密集した木に守られたけれど、子供は、あまりのことに目をまんまるくして泣き叫んだ。そして、この一帯で、竜巻の被害を受け補修を諦め新しく建て替えた唯一の家こそが、直前に竣工したばかりのぴかぴかの新築の家だった
冒頭に引用した長明の一文はこのように続く
よどみに浮ぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例(ためし)なし。世の中にある、人と栖(すみか)と、またかくのごとし。
われわれは、石造建築物の文化ではなく木造建築物の文化に育つ。石とは違って、木は湿気の中で早くに朽ちる。素材として元の姿をそのままに保つ時間/耐久性も石と較べて低いと言える。しかし、その分、素材としての再生は早く、われわれはその特質を理解し、家を、都市を、半ば壊れることを想定して築いてきた。栖(すみか)は、河を構成する水や速やかに老ていくわれわれ人と同じく、よどみに浮ぶうたかた(泡)と一緒だ、と長明は書いた
火災、地震、竜巻(辻風)様々な災害を実際に体感し、政治的な権力争いからはじき出され、ついぞ安定した仕事を得ることができなかった鴨長明は、彼なりの「安定」した住まいとしてタイニー(小さな)ハウスを建築した。『方丈記』の研究資料を読めば、長明が建てた方丈の家は今で言うリヤカーのようなものでの移動が可能だったみたいだからモバイルハウスでもあった。長明は、今でこそハヤリとも思われるタイニーハウス、モバイルハウスにいち早く目を付けた人物と言える。いや、目をつけたというよりも、長明自身が、小さく移動可能な家であったからこそ安住できた人であった。くどいかもしれないけれど、大切なので繰り返す。長明が、「強固」なことよりも「脆弱でない」ことを望み、そういう家を建てたのだ。明日、強い風が吹いて倒れてしまっても再建が安易だということを知ることで、それまで抱えていた不安を解消した、もしくはしようとした
経済的および政治的な側面で流通した2X4住宅、プレカット住宅、プレハブ住宅、ただのモダンな家に替わる、われわれの時代のわれわれの家、と呼びうるものが生まれくる時は満ちてきたと思っている
参考までに2012年5月6日に起きた竜巻の被害状況を以下に記しておく。益子町では死傷者が0名ながらも負傷者7名、家屋の全壊7棟、半壊26棟、一部損傷124棟。最も被害の大きかったつくば市では死傷者が1名、負傷者37名、家屋の全壊93棟、半壊197棟、一部損傷364棟(東京管区気象台より)。また、栃木で二カ所と茨城で一カ所、そして福島で一カ所発生した竜巻はもちろん同一のものではなく、それらは同時多発的に起きた
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.009
7年前に福島の16万の人が避難を余儀なくされたけれど、そのうちの半分以上およそ11万の人がもと住んだ土地へと還っていった。(2018年4月現在/福島民報)倒壊した建物を再建する、ということほど土地に付着したホウシャノウの問題はわかりやすくないからその人数が多いのか少ないのか、順調なのかどうなのか、ということは私にはわからない。ただどちらにしても、つまりは11万の人がどこかへと往ってそして故郷へと還ったことになる
どこかへと往って、そして還っていく。またどこかへと往き、そしてまた還る、、、
福島の人や、ましてやレースバトに限らず、生命は、この往って還ってを歴史上、いや、歴史など影も形もなかった大昔からなんどもなんども繰り返してきたのではないだろうか。往っては還り、還ってきてはまた往って、とにかく、いち、にー、さん、と数など数えるよりも昔からそれをひたすらに繰り返してきたのは事実だろう。海から陸へ、陸から海へ、アフリカ大陸から違う土地へ、その土地からまたアフリカへ、と。いや、海から陸へ、と書いてしまうことで省かれてしまうその間の往って還ってが数多くあったことは容易く想像できる。右後ろ足を海にどぶんと浸しながら陸地に置いた左前足が風に陽射しに曝されてからからと乾いていく、そういう永遠に近いと憶われる長さの時間を、われわれ、はじりじりと費やした。もちろん、そうした、という実感が今の、わたし、にあるわけでないけれども、地震によって起きた高波に襲われた2万人近いひとが「海へと還っていった」と表現することを社会として許しているのはきっと、わたし、の中にあるそれとおんなじ、われわれ、なのだと思う
2011年3月14日、フクイチが爆発する様をテレビで見届けると、私は、妻と子供の二人を栃木から実家のある東京へと避難させた。私自身は、その後どうするのかをネットで情報を集めながら検討を重ね、そして、ホウシャノウを封じているのも水、われわれの身体を構成しているのも水、なのであれば見極めるための基準もまた水にしようと「栃木の飲み水が汚染されたらひとまずもう少し西へと避難する」という指標を自分の中で設けた。そう思った時はまだそこまで汚染が拡大するとは思っていなかったけれど、フクイチめがけて上空からヘリの放水が試みられた17日の「為す術もない」ということを絵に描いたような様子に、もしかしたら、と思った。20日、飯館村の水道水から965ベクレルの放射性物質が検出された。私の住む栃木県は18日の段階で77ベクレルのヨウ素と4.6ベクレルのセシウムを上水(鬼怒川)から検出していた。21日になって、私は岐阜の親戚の家で家族と落ち合った
私と一緒に家族が益子へと還ってきたのは3月も末の30日。その間に何かが収束したわけではなかったけれど、ひとまずは住み慣れた場所に還ってくることを選んだ。わずか1、2週間離れていただけなのに、なんとなく、もう既にどこか何事もなかったかのように振る舞うカンジがほんのわずかだったけれどもちらちらと確認できた。子供が通っていた保育園の入園式もちゃんと予定にあったし、スーパーの棚に物が前のように戻ってきていた。その最中、4月の5日に、私は、映画をクランクインさせた。揺れていたものが定まっていこうとするその前にカメラをまわし始めた方がいいと思ったからだけれど、これは、長期的な問題なのだから長期的にカメラをまわすことになる、ということを実際にカメラをまわしはじめる側で感じていた。結局のところ、カメラは5年間まわし映画『ハトを、飛ばす』は完成した。いや、山崎農園にカメラを持って通わなくなった今もまだ、気持ちの中では、カメラをまわしている、というカンジがしつこいくらいにある。先にも書いたけれども、カメラをまわすことと山崎農園と一緒に生きていくということとが同義語に近かったから、ということとは別に、ホウシャノウ以降の今を観ていく、ということにおいてホウシャノウ以前の生活にはもう戻れないのだから以降ずっと観続けていかなくてはならない、という意味で、私のカメラは今もずっとぐるぐるとまわりっぱなしなのだろう。そして、相も変わらず私の思考は、同じところなのかそれともそれぞれに違った場所なのか、往ったり還ったりをぐるりぐるりと繰り返しているように思われる
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.008
数億年の歳月をかけて人間へと変貌を遂げたその最初の第一歩としてのミトコンドリアの命の営みいちいちに、人間へとたどり着く意志があったわけではなかった。それは、現れては消える波のように始まりも終わりもない様子でたんたんと、粘土をこねる水力の木槌が陶芸の里で土を叩くその音のごとく、ただただタンタンとタンタンと続いてきて、そしてその結果として、なんだかわからないけれどもわれわれみたいなヘンテコな生命に至った。そのヘンテコなわれわれはミトコンドリアとは違って、波が立てば嵐を思い、凪いだ海にこころを落ち着かせ、練り上がってくる粘土にそわそわとなる
ハトの映画を撮ろうと思いハジメたのは、311直前の年末だった。寝ていたのか起きていたのか、とにかく夢うつつのその最中に、けれどもやけにはっきりと「ハトの映画を撮る」のだということがわたしに知れた。そう思うに至る何かきっかけのようなものがあっても良さそうなのに、振り返ってみてひとつも思い出せない。ただ、ああ、わたしによって「ハトの映画」が実現するのだ、その時はそんな風に他人事のように枕元で思ったことを覚えている。とにもかくにもそれは決まったことだと思ったので、次の週、ハトを飼っている農夫に「ハトの映画を撮らせて下さい」と告げに行った。その農夫が飼っているというハトすらまだ一度もまともに見たことがなかったのに。そう告げてから、中古のHDカメラやDVテープをネットで買ったりして準備していると、突然311が起きた。ほうれん草が出荷停止になって農夫のことが心配で訪ねると、今度はその農夫の方から「ハトの映画を撮るっぺよ」と言われた。なんとなく、一緒に生きていくっぺ、そんな風に言われたような気がした
あなたとわたしが共に生きてゆく。生きてゆくためにはどこかへと向かう、漠然とでもいいから共通の物語が必要なのか。先に触れた母と子との関係のようなわたしもあなたもない状態においてはそんなことはなさそうだけれど、3人、4人、と複数の人々が、しかも赤の他人が共に生きていくために、ましてやうん億人とういより多くの人々が共に生きるためには大きな物語/幻想が装置として必要なのだろう。キリスト教が、イスラム教が、そして数々の国家と呼ばれる物語が、わたしとあなたが同じわれわれの一員であるということの囲い縄として機能してきたのは事実だ。しかし、その宗教も国家も、ここにきて、あまりにも大掛かりな笑えない嘘のように思われてきて、けれどもそれらに代わるものがまだ見当たらず、宙ぶらりんな感じがずっとある。幻想がとろけだしてほころんで、必至にそれらを繕う者の言葉の貧しさが、語られる世界/幻想をそのまま貧しく息苦しいものにしてしまっている。「自立した個人が一億総活躍できる社会」というのが、今われわれが自由なる意志で選択した権力者が掲げる世界/幻想であるのだけれども、語られているその側からその世界はしぼんでゆくばかり、もう、そういう言葉では1ミクロも先へとは進めそうにない
けれども、大きな物語が過去のものだとしたら、明日から生きてゆくための物語はどのように語られてゆくのだろう。小さなうた、小さな踊り、小さな器、小さな物語、、、?
もし、311がなければ、私は、実際にはハトの映画を撮らなかったかもしれない。いや、やっぱりそんなこともないのかもしれない。撮る、と思ったのだからどうしたって撮ったのだろうけれど、いったい311を経たあちら側の眼の存在なしに、私がどんな映画を撮れたというのだろう、はなはな疑問である。けれども現実に311が起きて、私はハトの映画を撮った。詩/踊り/器/物語は、数千年の歳月のあいだいくつもの編纂を重ねて伝承されて、私たちで終わるわけでも私たちから始まるわけでもなく、ミトコンドリアのようにただただ意志を持たないような在り方で、いま、ここを流れている。そして、われわれは、常にその流れの一途にいる。ハトの物語もまた、始まりも終わりもないくらいに昔からある物語のひとつに違いないのだから、私は、始まりも終わりもないその物語をただ、いま、ここで撮った、ということなのか
われわれは、自然の営みに寄り添って詩をうたい、踊りを踊り、器を焼き、物語を書く。ぶくぶくと泡が立つと、そのひと泡から詩/踊り/器/物語を掬いだし、どこかへ届け、と空に土に解き放つ。それらは止められてもわれわれが「やってしまわずにはいられない」事柄のひとつで、きっとこれからもそれをし続ける。詩や、踊りや、器や、物語は、目の前にはいない違う次元のあなたと結ばれるために形にされて(も)きたはずで、その、あなた、はもはや生きてすらいなくてもよい。大きいとか小さいとか、過去とか未来とか、生きているとか死んでいるとか、そういう次元からホップして、誰かと、何か手に取れないものと共に在るために、在るということを祝福するために、うたわれ、おどられ、つくられ、かたられる
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.007
2011年3月14日にフクイチが爆発して、放射性物質の拡散という新しく差し迫った困難から、逃げる/逃げないという二者択一を迫られた者同士の間を繋ぐ言語というのは当然のことながら存在していなかった。当時、全ての人が初めての事態に直面していたのだからその困難に対する行動の原理を、感情の揺れを、正確に言い当てる言葉など持ち得ていなかったのは当たり前のことで、だけれどもあれから数年が経ち冷静にある程度のことが情報として整理された今、その者同士を繋ぐ言葉は芽生えてきているのだろうか?
逃げる/逃げないという二項対立的なものの書き方を先にしたけれど、そう書いてしまった時点で、逃げる/逃げないということを判断するはっきりとした主体がどこかにあり、そうする、か、しない、かの意志はその強固な主体の内側に自発的に起きる、ということを想像させてしまう。自由に意志するのがわたしやあなたという主体であるということが確定的であればあるほど、する/される(逃げる/逃げられる)という能動と受動の関係にわたしとあなたは縛り付けられる。逃げたいけれどもそうしない/逃げたくはないけれどもそうする、という能動的でも受動的でもないゆく河の流れの如くに移りゆく「出来事」はあっさりと取りこぼされ、そうした/そうしなかった、というピリオッドのように釘打たれる誰それの「行為」のみが目に見えるものとして皆の前に居座ることになる
自分の意志で残ったのだから国の指示を受け入れろ、自分の意志で逃げたのだから福島のことに口出すな、こんな事態にまでなって福島に残るのは意志が弱いからだ、たいした被害でもないのに故郷を離れるなんて情報に流されているだけで意志が弱いに違いない。こんな古い言葉たちの応酬の中にあって、自分たちの言語が足りていない、という状況を確認し合うことは難しい。どちらかが「足りている」という勘違いの中に居残れば、その不足について確認し合うことは叶わないのだから
確かなる主体とそこに属する自由なる意志、そしていつでも求められる能動的な選択。わたしが、ここで、これをしている間に、あなたは、どこで、なにをしていたのか。誰が、どこで、なにをした、という言葉において切り刻まれた世界に閉じ込められた人は貧しく、そして脆い。かつて母から学んだやわらかな言葉は、世界を囲うためにではなく、それに寄り添うためにあった。そして、その内にあってわたしは豊かで、そして、けして脆くはなかったはずだ
わんわん、と泣いているわたしを見てただただ優しく微笑む母がいた。ばうばう、とわたしの言葉になりきらない声に主客をごっちゃにしながら言葉を重ねてくれた母がいた。一日一日の過程の内で起こるわたしにとっての出来事は、そうそう、と側でかけ声をかける母の内にも同時に起きていたのであって、わたしひとり独立したその内にのみあったわけではない。拙いながらもよちよちと歩くその歩行は、わたしと母との内に同時に存在した
もし、この母という言葉が、あなた、もしくは、われわれ、という言葉に置き換わることが可能なのだとすれば、よちよちと始まったわたしの歩行は、あなたと共に歩き続ける、ということの地平へと繋がっているのかもしれない
われわれは、言葉の不足に出会った。そういう「出来事」は、そのことに気がついた、わたし、と、あなた、との間に起きた。そして、それを乗り越えるための新しい言葉は、そのことを共通に体験した者同士の内に生成されるだろう。いや、既にあちらこちらにそういう言の葉(ことのは)が、舞を舞うようにひらひらと咲き始めているのかもしれない
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.006
地震と津波による被害について「方丈記私記」に記してから、次は原発事故の被害について書く必要があったけれど筆が進まなかった。被害の全容が見えないという事実もあるし科学的な知識の不足もまずはあるけれど、それよりも放射能にまみれた新しい世界の中で営まれる生活のことや感情を言い表す言語が現状では全く足りていないのだ。私は、震災後に映画『ハトを、飛ばす』の製作と随筆『土と土が出会うところ』をミチカケという地方紙に発表してきたけれど、これらはまさにその新しい世界に形を与えるための言語を自分の身体でつくっていくという試みであった。しかし、そうした後もいざ手持ちの言語で具体的に原発事故の被害について語ろうとすると、やっぱり言葉が足りていないという事実にいちいちぶち当たる。言語、というのは社会の中で共有されない限りにおいて言語とは呼ばないのだから、ひとつの映画、ひとつの本、ではどうにもならないということを痛感するけれど、その営みをやめようと思わないのは、われわれが使う言語の一部は(社会からではなく)文化からにょきにょきと発生して欲しいと思っているからだ
例えば、ということではないけれども「原子力の平和利用」という言葉は美しい言葉だなぁと思う。キャンプ場で焚き火をして暖をとるときに「火の平和利用」をしているなんてことをわざわざ言わないことを考えると、ますますこの言葉の美しさが際立つ。つまり、この美しい言葉が「原子力の(殺戮のための)軍事利用」と相対する言葉だと思っていいとしたら、「原子力の平和利用」という言葉は、原子力をより軍事的に利用をしていくためにぜひとも生み出したかった対概念だったに違いない。つまり、社会の中で頑張って頑張って捻り出された言葉ほど気持ち悪いくらいに美しいもので、(概念として正しいか医学として必要かは別にして「脳死」という言葉にも共通したすごみがある)その反対に、生活の中で使われる火についてわれわれが語るとき、それらの言葉は当たり前にすぎて美しくも何ともない
ただ、火そのものが生活の中から追いやられて久しいから、その当たり前の言葉ももうじき消えるのかもしれないけれど。私の住む益子という場所にはまだ囲炉裏の文化がしぶとく残っていて、その囲炉裏を挟んで語られる言語はそれを経験している者同士のなかにある
さて、その平和利用された原子力が爆発し、多数の被害を生んだのは2011年の3月である。地震によって発生した津波が福島第一原子力発電所(以下フクイチ)を襲った15時42分に、フクイチは電源を喪失している。そして、この電源の喪失がその後の爆発への全ての始まりだ、と東京電力(以下トーデン)は主張するが、世界中の原発事故の有無を監視するスウェーデンの施設が、11日の地震直後にキセノンという物質の濃度上昇が1,000倍に達した事実を指摘している。原子炉が壊れて最初に大気中へと放出される物質がキセノンで、その濃度が急激に上昇を示し始めた地点がコンピューターの解析でちょうどフクイチのある場所、そしてその時刻は原子炉の爆発が起きるずっと前の11日17時50分頃である、と同施設は導き出している。そもそも数々の欠陥が指摘され続けてきた原子炉マークⅠ型は、津波による被害(想定外)ではなく、地震(想定内)によっていちはやく崩壊していたことになる
トーデンは地震が起きた翌日の12日午前11時の記者会見で、爆発によって放射性物質が大量に飛散したときの避難方法を住民に伝えるよりも先に計画停電の可能性を示唆した。そして、その発表の少し後の15時36分にフクイチの1号機は水素爆発を起こす。14日には3号機が爆発し、続いて15日に4号機が爆発した
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.005
統治権力の中心が朝廷から武家へと劇的に移行した鴨長明の時代は、地震、大火、竜巻、飢饉などの災害も頻発し、政治における猟官運動、神官や僧侶の地位争い、さらには法然、親鸞、日蓮らに対して行われた思想弾圧に至まで、今よりも絶望的な状況だったと言えばそうかもしれない。しかし、混乱という意味では、現代もそうとうなものだ。長明は、数々の災害現場を目の当たりに(経験)したが、原子力発電所の爆発およびその放射能被害は当然の如くに経験していない。つまり、われわれは、長明が経験していないしごく現代的な問題にぶちあたっているわけであり、きっとこれからも、あたらしい災害/人災にぶちあたり続けるであろう
けれども、長明(鎌倉)や堀田善衛(昭和)の時代とともに共通したこととして、混乱を引き起こした政治が結果責任を問われそれに対して自らケジメをつけるということは一つもしたためしがなく、この度の原発事故についてもそうであった。そして、それを許し続けている、われわれ、が過去にも現在にもいる。堀田氏はこのことといわゆる「無常観」とはなんの関係もないことであるとしつつ、われわれを根底から捉えて離さない無常なる感覚は十二分に政治利用されてきたことを指摘したし、今も、そのことに変わりはないだろう
私が、映画「益子方丈記」の製作を通してやりたかったことといえば、もちろん、「わたし」という主体を表出させることではなかったし、ましてや「方丈記」における「無常観」の側面を強調したかったのでもなかった。堀田の言葉を借りれば「われわれの思想生活の根源に生きて横たわっているものをともにえぐり出して見る」ためであり、そして、戦争に負けて期待された「あたらしい日本(堀田)」の実現が遠の昔に挫折した今となって、長明のように田舎へ籠り自己一身に絞って庵を結ぶのでもなく、なにか数段飛び越えて「みんなの家」なるものを被災地に建設するのでもなく(このように書くと、どうも日本人的な感情として私がそれらを否定しているかのように捉えられがちだけれども、そのつもりはない)むしろ、われわれの骨の髄にまで食い込んでいる無常なる感覚に「わたし」の中でしっかりと向き合いつつ、あたらしい「あたらしい日本」ではなく、あたらしい「われわれ」が生起してくるのを(長明が持ち得なかった)「眼」と「耳」を携えて、待っている、という態度をひとまずは表明することであった
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.004
震災後、床に散らばった本ひとつひとつを本棚に入れなおしたけれどもしばらくはちっとも読む気がしなくって、けれどもふと背表紙が光って感じられた7月、久しぶりに手に取って読み始めた本が森有正のだった。リハビリをするようにたどたどしくも指でなぞりながら読み進めたその69ページ目に「われわれの」と呼ぶことができる言葉がそこにあった。私はのこのことこの言葉を求め探し歩いたのではなく、そもそもに、この言葉の中で立ちすくんでいたのだ
この間、あるフランスの若い女性が尋ねて来た。大学内ゴルフ場内のレストランへ案内して話をした。緑にかこまれた食堂では、何人かの人々が静かに食事をしていた。生粋のパリ育ちのこの女性は数年間を日本で過したのである。私達はよも山の話をしていたが、やがて話は日本における生活、ことに東京の生活のことになった。どういう話のきっかけだったか忘れたが、というのはその時かの女が言ったことばに衝撃をうけて、何の話の中でそうなったのかよく記憶していない。かの女は急に頭をあげて、殆ど一人言のように言った。「 第三発目の原子爆弾はまた日本の上へ落ちると思います。」とっさのことで私はすぐには何も答えなかったが、しばらくしても私はその言葉を否定することが出来なかった。それは私自身第三発目が日本へ落ちるだろうと信じていたからではない。ただ私は、このうら若い外人の女性が、何百、何千の外人が日本で暮らしていて感じていて口に出さないでいることを口に出してしまったのだということが余りにもはっきり分かったからである。かの女は政治的関心はなく、読書も趣味も友人も、ごく当り前の娘さんである。まして人種的偏見なぞ皆無である。感じたままを衝動的に口にしただけなのである。
胸を掻きむしりたくなるようなことがこの日本で起こり、そして進行しているのである。
かの女がそう言ったあと、私は放心したように。大学構内の木々が日の光を浴びて輝くのを眺めていた。 (『木々は光を浴びて』森有正)
この言葉が書かれたのは1970年の11月。本を手にした私の心臓がばくばく鳴って足が震えたのが2011年の7月。そして、まさに、胸をかきむしりたくなるようなことがこの日本で起こり、そして進行しているのである。われわれはそのことをつかの間、忘れていただけなのだ
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.003
東日本大震災が起きたそのとき、私は、文字通り揺れのまっただ中にいたからどこが震源地なのかと東を向くことも西を向くことも頭に浮かばず、ただただ、建てたばかりの家が崩れぬことを身体から絞り出すような気持ちで祈った、その祈ったという感情を、今のことのように思い出す
あの日、妻の腕の中には1歳かそこらの幼子がいて、その姉は保育園に行ったまま姿はなかった。揺れは何分か続き、おさまったと思ったらまた大きく揺れること数回、幾度そんなことが繰り返されただろうか、外に置いてあったテーブルが割れた地面へと吸い込まれていく様や、木々が揺らされ巻き上げられた花粉が空を不気味な色に染めていく様を半ば他人事のように眺めながら、ただただ、建てたばかりの家が崩れぬことを祈った
今、ここが揺れている、、、他でもなくここが揺れているというのはどうしたって「わたくしごと」になるのだろう。けれども、想像を越えた力が地面を動かしているのを目の当たりにすると、事が「わたし」の事であると根拠づけるはずの私の身体の小ささが強調されてしまって目の前で起きているほとんどの事が、私事ではない他人事として感じられてしまう
自然の声が聞こえる、万物と私とに境はなく全て一体である、と言ってしまえる可能性に対する日々の疑いのなか、地球という惑星の上で木も土も家も私も等しく揺れ踊っているという全体性を伴った他人事のような感覚は、どこからやって来たのか。しかし、であれば、激しい揺れのなか、他人事のように笑けてしまう揺れのなか、一神教を信ずるわけでもない私が自己中心的に祈った対象として私ひとりの神はどこからやって来たのか、祈った「私」はどこから来たのか
あの日に感じた私と「わたし」、世界と「せかい」とのズレが、今、とても気になる
さて、私もあなたも感じた揺れ、そして揺れた事との物理的な距離は、客観的に以下のように整理されている
2011年3月11日に起きた東日本大震災の震源地は三陸沖であり、マグニチュードは9.0。最大震度は宮城県の栗原市築館で7、遠くはなれた鹿児島県でも震度1を記録。そして、<主だった>地域の震度は以下の通り
6強:宮城県塩竈市、福島県国見市、茨城県日立市、栃木県真岡市。6弱:宮城県石巻市、福島県郡山市、茨城県常陸太田市、栃木県芳賀町、岩手県一関市、群馬県桐生市、埼玉県宮代町、千葉県成田市。5強:宮城県気仙沼市、福島県白河市、茨城県常陸大宮市、栃木県益子町、岩手県釜石市、群馬県高崎市、埼玉県熊谷市、千葉県香取市、青森県八戸市、秋田県秋田市、山形県米沢市、東京都荒川区、神奈川県横浜市、山梨県忍野村、、、、、(気象庁HPより抜粋)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.002
「私が以下に語ろうとしていることは、実を言えば、われわれの古典の一つである鴨長明『方丈記』の鑑賞でも、また、解釈でもない。それは、私の、経験なのだ」(堀田善衛「方丈記私記」)
この文章を堀田善衛は「方丈記私記」の頭に置いた。私も、そのままこう書いておく
私が以下に語ろうとしていることは、実を言えば、鴨長明「方丈記」もしくは堀田善衛「方丈記私記」の鑑賞でも、また、解釈でもない。それは、私の、経験なのだ
さて、なぜ今「方丈記/方丈記私記」なのか。そんなことはわからない、というのがその答えだけれど、そもそも東日本大震災が起きてから「方丈記」が気になり始めたわけではなくて、「方丈記」の映画化は、映画「ハトを、飛ばす」と同様に東日本大震災の前から考えていたことなのだ。つまり、「ハトを、飛ばす」と「方丈記」のことをつらつらと考えている最中に、私は、東日本大震災を経験した
私が経験した東日本大震災の前に、私を含めたわれわれが経験した東日本大震災のことをまずは記載する
平成23年に起きた東北地方太平洋沖を震源とする地震のことを、現在ではおおむね東日本大震災と呼んでいる。発生した月日から311と呼ぶこともある。アメリカで起きた同時多発テロが911と呼ばれたことに起因していると思われるが、これは、この事件が人々の脳裏にひどくこびりつていることを物語るだけなのかもしれないけれど、地震によって誘発された原発事故という人災の側面と重ねられている可能性もある
被害を数字で計ることはもともと難しいことである。遺体や行方不明者の数を数えるか、倒壊した建物の数を数えるか、それくらいのやりかたしか思い当たらないのは私も一緒である。その数、警視庁の平成29年6月の発表で死者15,894人、行方不明2,550人、負傷者6,156人、建物の全壊121,770戸、半壊280,286戸、全焼半焼合わせて297戸、浸水した建物13,583戸。平成24年2月、つまり震災からほぼ1年が経った時の警視庁の発表で死者と行方不明をあわせて19,131人。現在の発表の18,444人と較べ700人ほどの開がある
避難生活によるストレス死を含む震災関連死という言葉があって、その数は、復興庁の発表によると平成29年6月の段階で3,591人。さらに原発の被害に限っていうと平成28年3月の東京新聞による集計では1,368人。警視庁の調査で死者行方不明者の数が年々増えてゆくのならわかるけれども、減っていることの意味は私にはよくわからない。扱っている対象が違う恐れがある。さらに、復興庁の数字に原発事故の関連死が含まれているのかはわからない。放射能の影響による健康被害を国はほとんど認めていないので、それをどのようにこれから計っていったらいいのか、私には今のところ皆目見当がつかない
ある側面で、被害は被害者が語るしかないのかもしれない。時にそれは長い時間の沈黙となって現れる死者の声も含めてなのだが、被害者が被害を語ることを許すということ、「わたし」と「あなた」との間において実践されてゆくことが、私は、とても大切だと思う。それを許す「わたし」と「あなた」との関係を「われわれ」と呼ぶのだと思う
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
方丈記私記[平成]No.001
2011年の震災の頃のことを思い返すと、真っ暗な夜空に輝く星の光がまず思い浮かぶ。たぶん、数日後に原発がどかんとなった際に感じたあの底なしの恐ろしさの対比として、あの星がよけいに記憶の中でまばゆくひかるのだと思う。映画『ハトを、飛ばす』を撮ることは震災前から決まっていたけれど、撮影が開始され、そして映画がどうにもこうにもとりあえず完成したのは、その光と、その得体の知れない恐ろしさがいつまでも私の中にしつこく残っていたからだと思う。
また、ミチカケにも書き下ろした『サンコウチョウ』という文章もまた、同じようにその光と、その得体の知れない恐ろしさから発生したように思う。
恋するあの子のうしろに落とした尾が地面にそのままで、こころ踊って舞を舞う。暗闇の中から飛び出して、ホイ、ホイ、ホイ、夜空に散らばる星となり、百万年後の光源のことなどつゆ知らず。暗イウチハマダ滅亡セヌのなら、目を閉じることにも価値はある。目を閉じると闇がある。一周ぐるりとまわって触れたかったあの子の肩が、その闇にある。その闇のなか、長い長い尾が限度もなく落ち続けている。その落ちた尾を追う者はない。(ミチカケ/土と土が出会うところ/サンコウチョウからの引用)
「差異」が表現を可能としてくれるのだとしたら、あの光と、あの得体の知れない恐ろしさは確かに平和な日常からずっとずっとかけ離れていた。
けれども、表現するに値する差異は、日々平々凡々に繰り返される毎日にも溢れている。鳥が「ツキヒーホシホイホイホイ」と鳴くんだよと益子の陶芸家が教えてくれて、実際に、その鳥がツキヒーホシホイホイホイと鳴いているのを聴き、鳥は私のなかでサンコウチョウという名を与えられた。今まで聴こえていなかったその鳴き声が私のものとなると、私の家の森でも、時折鳴いていることに気がつくものなのだ。
差異はそこかしこにあって、つまりは「そこ」に意識を合わせるのかどうかということなのか。いや、私という実体と対象という実体があってそこに交感があれば(実体と実体が出会えば交感は無条件でうまれる)差異は関係ないとも思えてくる。意識されるのを待っている「それ」が無意識だとして、「それ」を意識して抑圧から自由になるために脹らませる必要があるのが自我なのだとすれば、「それ」などもともと取るに足らない、ということにならないか。ツキヒーホシホイホイホイ、「それ」が意識されるよりも先に音がある、そう思う