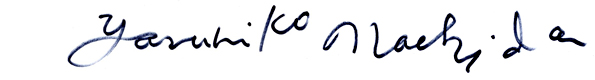ふたりのあいだ
水曜日, 1 7月 2020

ざーざーざー、と寄せては返す波の音がする。波を砕くテトラポットも波を防ぐ防波堤もなんにもない世界で、海の温かさを共有しながら波打ち際でひたひたとふたり戯れている。波の音を打ち消してしまわぬよう慎重に言葉を探しながらぽつぽつとふたり語り合っている。
「美しい山という時の美しさと、美しい海という時の美しさは同じではないよね」
「うんうん、同じではないよね」
「私は、美しい海と言うほどには山のことを知らないけれど」
「うんうん、それはどのような関わりを持つのか、ということに違いない」
「いや、私には海のこととて美しいとはまだまだ言えない」
「うんうん。最近、粘土を手にすることが増えて私は山の存在がとても気になっている」
「うん、そうだった」
「でも、その山のいただきに海の痕跡であるチャートを拾うことがある」
「うんうん」
「波打ち際の砂の表情のように人間は消滅するって言う時の人間に、ついぞ私たちは乗っからなかった」
「うん、乗っかったためしはなかった」
「美しい山と言う時の美しさか」
「うん、山が美しいと言う時の山か」
ひっつきながら話していると互いの主張がこんこんと混ざりあっていくような感覚があって、うんうん、とする相槌ももはや自分に向かっているのか相手に向かっているのかわからなくなる。そういうことがどんどんとわからなくなって闇も深くなり、ヒーナは寝ているのか、起きているのか、死んでいるのか、生きているのか、その彼岸と此岸の両方の縁に触れているような気分にしっとりと沈んでいくのだった。そして、ふたりのする話はいつまでも進化過程の両生類みたいに、一歩陸地に這い出してはずりずり海へと踵を返す、そんなまどろっこしい停滞の中にあった。まるで、終わりと始まりが同時にその波打ち際にあるかのようだった。ヒーナは「ねぇ」とすいに声をかけた。すいは「なに?」と返事をした。ヒーナは、ねぇ、よりも先に言葉を足さなかった。すいは、なに?、よりも奥に言葉を探さなかった。ねぇ、と言った時、ヒーナはもうはんぶん寝入っていた。ヒーナの身体がぴくりとミオクローヌスを起こしている。それはもしかしたら人が水の中で息をする生き物へとゆっくり変成を遂げているその微かな兆しなのかもしれない、とすいはヒーナの身体に触れながら思ったのだった。
絵:笑達
文:町田泰彦