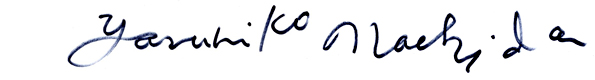火と水と
金曜日, 1 11月 2019

方丈記私記[平成]No.017
言語矛盾かも知れないしずいぶんな放言になる恐れもあるかもしれないけれど、万物の根源が「水」であるのか「火」であるのかというその「根源」もしくは「根拠」について、実は、タレスもヘラクレイトスもそれほど執着していなかったような気がする。むしろ、火に当てられ水を沸かすことを可能とする「器」であるところの「万物の~」と言うその時の<感覚>もしくは<意識>の発露にこそ、彼らはこだわったのではないだろうか。だからこそ「万物の根源は数字である」と言い、根源(アルケー)であるところの数字の方に執着したピタゴラスに対してヘラクレイトスは烈火の如く怒ったのだと思う。そして、その器であるところの<感覚>なり<意識>というものの「深さ」がベースとしてわれわれに備わっていることは確かなジジツで、なぜなら、タレスでもヘラクレイトスでも誰でもいいけれど「万物の~」と言うことが可能となった瞬間に語られる「万物」という意識の中には、わたしもあなたも、土も木も風も、虫も粘菌類も、爬虫類もシダ植物も細菌も、全部がぜんぶ含まれているからである。その意識が存在する場所では時間も空間も無化されているから、つまり、2500年前にタレスやヘラクレイトスが「万物の~」と語ったその瞬間の彼らとわれわれはまさに垂直的に「万物」の中にあって、あっちからこっちという指向性もなくまるっと一緒くたになっているのだ。そして、その意識の中で全てのものがまるっと存在する場所のことを、時に、われわれは「誰のものでもない場所」とか「何処にもない場所」とか、はたまた「ユー・トピア」と言ってきた
「文学は、自らそれが何であるのかを言うことはできません。ただ繰り返し繰り返し千年以上にわたって自らをいかがわしい言葉に対するアンチテーゼ、と見放してきました。実生活はいかがわしい言葉しか持っていないからです。ですから文学はそれに対して言葉のユートピアを対置させてきたのです。この文学は、たとえそれがどんな時代とそのいかがわしい言葉に準拠しているとしても、絶望しながらこの言葉に向かって歩いてきたが故に讃えられるのであり、人々の誇り、希望となるのです(中略)その予感された言葉に向かう方向としての文学を書き続けなければならない」
こう語ったのは、自らはルーマニアの強制労働所をかろうじて生きのびたけれど両親をドイツの強制収容所で失った世紀の詩人、パウル・ツェランそのひとである。ツェランは、戦後においてもなおはびこっていた反ユダヤ主義的雰囲気の中で、誰のものでもなく何処にもなく境界のない世界に、詩、でもって向かっていった
ユダヤ人であるツェランと意識を共にした数少ないひとのなかに、オーストリア人であるインゲボルグ・バッハマンという詩人がいた。このふたりの間で交わされた書簡が、今に生きるわれわれには痕跡として残されている。ふたりは、古い言語がつくった境界(時代)を突破するための「新しい言葉」を、新しい意識でもって触れられる「場所」を、戦後の世界に共に求めた。時に励まし合いながらユートピアの光の中で詩作を通して生涯その実践をし続けた
第二次世界大戦の傷跡が残る占領下のウィーンで出会い、そして互いに愛し合うようになるまでにはたいして時間がかからなかっただろう、その納まり方は、まったくもってシゼンなはずだった。しかし、ツェランは、新しい世界の新しい言葉を探すよりもその遥か前に、古い言葉によって、制約の総体としての言葉によって深い傷を負ってしまっていた。彼の心と身体には、深々と古い傷が刻まれていた。そしてその傷は、ツェランを古い世界に束縛し続けるには十分すぎるくらいの、静まらない、鈍い痛みとなってずっとずっとそこに在り続けた。男であるのか女であるのか、ユダヤ人であるのかドイツ人でるあるのか、ヨーロッパなのかアジアなのか、家庭があるのか独り身なのか、傷を負っているのかむしろ時代の恩恵を受けているのか、つまりそういった世界を分かつもの、断つもの、境界、世界を分断するその溝に、穴に、終始オトコはトラワレ続けた
自分がナチス党員の娘として不自由なく生まれ育ってきたというジジツもまたツェランを苦しめていることを知っていたバッハマンは、詩人として結局のところ言葉では超えることができないものがあるという行き詰まりにあった男を、けれども辛抱強くこう励まし続けた「さぁ、私たちは(新しい)言葉を見つけましょう!」と。そして、深く包むような眼差しでもって、愛、にもまた新しいカタチがあることを男に示し続けた。男が死んでからもいっそう頻繁に、さらに切実に、、、
ツェランは1970年(昭和45年)に、水によって死に(入水自殺)、後を追うようにバッハマンはその3年後の1973年に、火によって死んだ(寝たばこによる重度の火傷)。物理的に火と水は出会わない。それと同じように男と女はシゼン現象そのまま、互い、はじきはじかれてこの世界から消えていき、消えていったその先でも交わらずにいるのだろうか?
ツェランとバッハマン、そしてバッハマンとツェランの妻との間で交わされた書簡が『バッハマン/ツェラン往復書簡 心の時』(青土社)としてまとめられていることは先に書いた。600ページに迫る大著だけれど、この本には、ツェランとバッハマンとの距離、ツェランとツェランの妻との距離がそのまま、もう、触れられぬ、という痛みとして、残されている。世の中のひとに「ひと」が見えるのは(むしろひとばかりがみえるのは)自分とひととの間に距離があるからだけれど、ツェランが死に、バッハマンが死んで距離が失しなわれて、それでも、いや、だからこそ、そこに(本の中に)愛だけがぽつねんとあるのが、わかる。その微かなぬくもりが読後の「わたし」に広がってくる。数々の詩や優れた文学を世に送り出した彼らだけれど、ふたりにしてみては、「新しい言葉」というものをついぞソウゾウすることが出来ず失意の中に死んでいった、ということになるなのかも知れない。しかし、この、行ったり来たりした意識の痕跡としての文学に、「男の意識」と「女の意識」はたまた「ユダヤの意識」と「それ以外の民族の意識」という制限をゆうゆうと超えていっているそのサマがぼわぼわと滲んで見える。そして、ふらふらと世界の全体がにょろにょろと顔をのぞかしているのがカンジトレル。隠れたはずのピュシスが、彼らが見失った愛が、今、ここに、ほら、と顔をのぞかしているようである。そして、本を閉じると、バッハマンがツェランに、さあ、と促し続けた言葉がそのまま今に生きるわれわれを促す言葉として、ぼーぼーと聴こえくるようである「われわれは、われわれの時代の(新しい)言葉を見つけましょう!」と
そう、私には、聴こえる
そう聴こえると思うのは、ややロマンチックに過ぎるのかもしれない。だけれど、彼らが死んで触れられるものとしての存在から離れていったその場所がわれわれにはすっぽりと隠されているのであるから、彼らが今、ふたり、水となり火となってそれでもなお寄り添っている、という風に考えることもできるし、考えないでいることもできる、ということなのだ。「同じ河にわれわれは入ってくのでもあり、入っていかないのでもある、存在するのでもあり、存在しないのでもある」ヘラクレイトスは2500年前にそう言った。そして、その1700年後に、同じ(ような)河の流れを見ながら鴨長明は、自分の渇望を断ち切るために出家した。ひとはひとの権力に対する執着を汚ならしいものを見るみたいに見るし、そのくせ彼のようなひとのことを敗北者とらくらくと烙印を押す。けれども、そんな烙印を押された彼はひょうひょうと、誰のものでもない場所をただただ誰の意識でもない意識で見ようとしていただけなのかもしれない、と、わたし、なんかは思ったりする